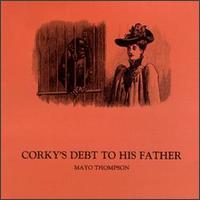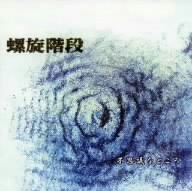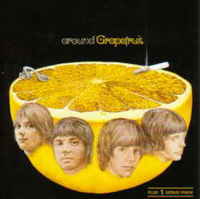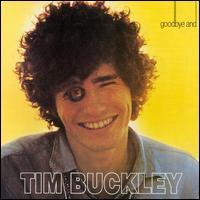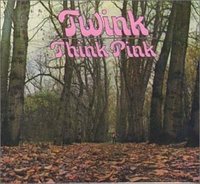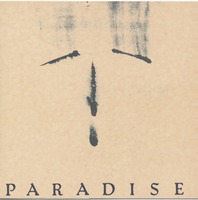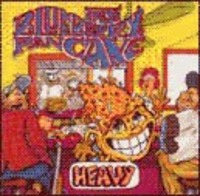凝解、その後 書き手・森本
世の中の右と左そしてうしろ 暗がりで笑う人をみたときや 銀行のATMで現金を取り忘れたときに なんとなく読むブログ
カテゴリー:サイケ
2007年04月11日
BOBB TRIMBLE 「Harvest Of Dreams」
82年になぜこんなスタイルの音楽をやっていたのかはまったく謎だが、とにかく極上のアシッドフォーク。
この人間離れした、年齢や性別など一切感じさせない歌声は一体何なのだろうか?
色んな意味で怪盤である。
彼にとって、音楽とはなんだったのか? また、サイケデリックムーブメントに10年以上遅れて登場してしまったことをまったく気にしていないその孤立感はいったい何を根拠にしているのか。
謎に包まれたBOBB TRIMBLEであるが、アルバムタイトルの通り、夢の収穫のようなサウンドが全ての解答であるのかもしれない。
ひたすら透明な、向こう側の歌である。
2007年03月01日
MARK FRY 「DREAMING WITH ALICE」
晴耕雨読なスタイルでの臨死体験か。
やわらかいファンタジーの装飾があったとしても、根底ではまったく作為的ではないものの影響が大きく表出している気がする。
マーク・フライの名がアシッド・フォークやドリーミー・サイケ好きの間で騒がれていたのは、何度も色々な形で出されるブートでも分かるとおりだが、正式に再発された今もなお、その良質な音楽が評価され続けているというのは、やはりここにある世界が本当に良いモノだからだろう。
不思議なノスタルジーと心地良い音色を期待して聴くと、意外にバキバキ弾くギターの音のかっこよさに少し戸惑う。だが、そこがまた良い。
このアルバムはある種の理想であると思う。ソロでアルバムを作るならば、誰しもがこんなアルバムを作ってみたいと思うのではないだろうか。
断片的に挟まる曲、DREAMING WITH ALICEの滑らかな感触がこのアルバムをここまでの名作にまで昇華させている気がする。
2007年02月23日
Mayo Thompson 「Corky's Debt To His Father」
The Red Crayolaに衝撃を受けた後に本作を聴き、Mayo Thompsonの世界にどっぷりとハマッた。
なんとも不思議によれよれした状態で漂ううたがなにしろ強烈。牧歌的ではあるかもしれないが、不思議と酩酊するような毒がしっかりと混入されている。
ここまで美しくもひねくれた演奏というのはなかなか聴けるものではない。まさに歴史的な名作だと思う。
フォーク的なサウンドではあるけれども、The Red Crayolaでのメイヨとまったく違うというわけでもなく、同じような精神性は確実に存在している。
これが苦手だという人がよくいるけど、たぶんカッチリした演奏とか、しっかりした構成の楽曲じゃないと聴けないタイプの人なんだと思う。聴き手も、もっと自由に聴いた方が楽しめるのに、と思ったりもするのだが…。
2007年01月23日
MARTHA By Kamijo
ホンモノのレア盤としてよく話題に上がる本作。現物は見たこともないが、あったとしたら信じがたい値段がつくそうな…。
某海外レーベルより半分ブートみたいな感じでちゃっかり再発されていたが、それももうほとんど売り切れらしく、結局また聴きたいけど聴けない、という人が出てきそうな予感がする。
内容はかなり良質なサイケデリック。わりかしドラマティックかつやわらかめな質感。何度聴いても美しい音楽だと思う。
Tomoaki Kamijoという人がミュージシャン気質な人物だったのかどうかは知らないが、かなり完成度の高い楽曲が並んでいる。ボーカルも味があり、翳りのあるメロディがなんとも渋い。ファズのかかったギターも鳴るが、全然うるさくなく、統一された静かな風景がより一層クリアに見える仕掛けには「はっ」とさせられたり。
これものんびり家でごろごろしながら聴きたい一枚である。 が、朝から聴くと、まったりし過ぎて家から出られなくなるので注意。
日本のロック史上にうっすらと輝く名盤。
2006年09月08日
SPIKE DRIVERS
ヴェルヴェット風味と言われればそうかもしれないけれど、VUと同時代にこのサウンドという事実が興味深いのであって、ここにVUと同じ深淵を覗こうと思って大金を支払うのはやめておいた方がいい。
60年代のデトロイトにこのような音楽が! という驚きを感じないという人にはまったくオススメできないけれど、当時のサイケデリックを掘り下げようとしている方には必ず聴いておいて欲しい一枚だと思う。
エコーのかかり具合が何ともいえない美しさで、遠方の駅の改札まで来て切符を落としたことに気づくような絶望もややあり。
ポップなエッセンスもあるので、マニア以外の人にぜひ聴いてもらいたいアルバムである。
2006年07月25日
螺旋階段 「不思議なところ」
螺旋階段は渦を巻いたような形状の階段であるが、一部分だけを切り取れば、それはただの階段にしか見えない。全体を把握して初めてそれが螺旋階段であるという判断に至れるわけだ。
この螺旋階段が後に非常階段へと発展し、音楽性がノイズ・インプロヴィゼーションに変化した背景には、おそらくそれほど大きな転換は無かったのではないかと思える。
ここで聴けるサイケデリックなロックは、既に音楽としての位置づけを拒んでいるかのような見事な跳躍で真っ白な空へ飛び去っていった。
あとに残された群衆の顔には、夏の日焼け痕を思わせるような黒い染みが、いつまでも残った。
真実としての演奏ではなく、演奏が真実であるならば釈明は必要とされない。
螺旋階段の中で立ち止まり、捩れているものが自分だと気づくまでの、一瞬の空白がたまらなく好きだ。
2006年07月13日
Judy Henske & Jerry Yester 「Farewell Aldebaran」
もともと、Judy Henskeはジャジーなシンガーとして活躍しており、夫のJerry Yesterはラヴィン・スプーンフルにも在籍していた。
この夫婦が共作で作り出したアルバムが、ど真ん中のサイケデリックであったことがまず驚きである。
この後に別名義で出した2ndではフォーク風になるのだが、ここではJerry Yesterの手腕が大いに発揮され、バラエティに富んだポップな世界が展開されている。
オリジナルはザッパのレーベルから出ていたが、入手困難。最近CD化され、安価で購入できるようになったのが嬉しい。
どこかでこのアルバムがスラップハッピーのようだと書かれていたが、私はそうは思わない。スラップ・ハッピーの捩れたまま生まれてしまったような必然のサイケデリックとは違い、このアルバムは夫婦のほのぼのとした、日常を拡大した際の装飾品としてサイケデリックが選択されているのだ。
だから、表ジャケットがサイケな色をしているのに、裏ジャケットはほのぼのとした普通の写真が使われているという「日常の副産物」を感じさせるイメージが表出している。
かといって、中身は平凡なサウンド、というわけではない。この夫婦の共同作業によって作られた音楽は、カラフルで非常にクオリティの高いポップ・サイケである。ただ、酩酊するだけのトリップ感を誘発するサイケよりも、こういった日常的な遊び心の拡大によって零れ落ちたサイケの方が、休日にゆったりと鑑賞するにはちょうどいい。
2006年05月23日
Grapefruit 「Around Grapefruit」
名の知れた名盤である。
でも、この変なジャケットのせいでまだ聴いていないという人も多いと思う。
かなりポップで、聴きやすいソフトサイケだが、果たしてこれをビートルズフォロワーの一言で片付けてしまってもいいものなのだろうか? たしかに名づけ親がジョン・レノンであり、アップルと契約までしたものの、ビートルズの付属品として語られるだけではあまりにももったいないバンドである。
フォー・シーズンズのカバーである「C'mon Marianne」以外はすべてオリジナル曲なので、やはりバンドとして素晴らしいグループだったことを再認識させられる一枚である。曲のクオリティがとんでもなく高いので、B級だのなんだのと言うのはこれときちんと向かい合っていないリスナーの妄言であろう。
極上のポップサイケに触れたければ、まずはここから。オススメです。。。
2006年05月20日
GEORGE BRIGMAN
2006年05月18日
Mascots 「Ellpee」
サイケどっぷりというより、前夜、といった感じか。
メロディも構成も文句無しに高いクオリティであるが、レアな一枚になってしまっている。
一応CD復刻され、簡単に入手できるようにはなっているが、知名度が恐ろしく低いゆえにたぶん誰も買おうとは思わないだろう。
この時代のロックを聞いてみよう、と思ってから、人はまず何から聞くのであろうか?
ビートルズ、もしくはストーンズの「サタニック~」あたりなのだろうか?
もしあなたが今「サイケなロックをとりあえず一枚聞いてみたい」と思っているなら、こういったかつての埋もれた佳作を手にとってみることをおすすめしたい。
B級だのなんだのと言っても、それは後から他人が評価したことに過ぎない。やはり自分の耳で、好きな音楽を純粋に探していくという行為は、それだけで素晴らしいことだと最近思ったりする。。
2006年05月16日
FICKLE PICKLE 「Sinful Skinful」
これは凄い。とにかくポップサイケの良質な部分が凝縮されている大名作。
紙ジャケでリリースされていたので、ちょっと高かったが購入して正解だった。
内容はビートルズの影響大のサイケデリックポップ。で、ドリーミーな効果音や激しいファズギターも聴ける充実の一枚である。
こういった埋もれた名盤を今聴きなおす感覚というのは、懐古的な感覚ではなく、素直に新譜として受け入れるような姿勢でのぞみたいものだ。新しい音楽として知ることができれば、それはその音楽本来の価値観を見つめることが出来るだろう。
サイケに関しては、特に聴き手のそういった心構えが重要になってくると思う。
2006年05月15日
PUSSY 「化け猫ロック」
これ、レアでマイナーなサイケだったんだけど、この前CD屋で普通に紙ジャケ再発されててびっくり。
こんなものまで出るんだ~、と呆れたような感心したような。
化け猫ロックって、邦題もアレだけど、中身はもっと凄いことになってて、これはぜひサイケ好きは聴いておくべき一枚だろう。
私の持っているやつは輸入盤だけど、国内版の紙ジャケのやつはたぶんリマスタリングされてていい感じだと思うので、そちらをオススメ。
最近またこういうサイケの名盤(?)を集めたくなってきたので、ブログの更新も滞っていることだし、サイケ特集をやっていこうと思う。
まだまだこのジャンルは開拓しがいのある分野ですし。。
2006年03月20日
Tim Buckley
ティム・バックリィの悲痛な感覚はまだここでは表立ってはいない。
彼がただのシンガーソングライターの一人として語られないのは、その世界の深さが底なしに広がっているからであり、サイケデリックが局所的に訪れていた季節ではなかったことを思い知らされる。
ファンタジックな広がりではなく、わりと人間的な臭みを含んでいる部分も良心的と言えるかもしれない。ティム・バックリィのサウンドや詩は確かな手ごたえのようなものを聴き手に与える。
ジャケからカントリー風の演奏をイメージするかもしれないが、ここにあるのは紛れも無いアシッド漬けの心象風景である。
聴くにはそれなりの覚悟が必要だが、深いダメージを受けるような歌ではないのがせめてもの救いであろう。
歴史的傑作。
2006年03月13日
TWINK 「THINK PINK」
よく言われる「名盤」といった感じの華やかさよりも、しっかりとした表現の力強さを感じる良作だと思う。ピンクスもいいが、たまにはこっちも聴くとバランスがとれ、思わぬ袋小路へ迷い込むというような失敗は免れられるだろう。
こういった有名なレコードは、まずジャケットのイメージが広く伝播し、次に中の音を聴いてショックを受けた者たちが、まるで神秘体験でも語るかのように口伝していくものである。
キツネでも憑いたかのような目つきで、熱っぽくこういった音楽を語ろうとも、本質的な部分でそれが相手に伝わることは少ない。だから、こういったものを紹介したいのならば、まずはその音を実際に体験してもらう必要がある。
だが、大抵の音楽ファンはそこまでして他人のオススメするレコードを聴こうとはしない。なぜなら、説明の最中に彼らは「この音楽については認識できない」と判断してしまうからであり、無意識のうちに拒絶してしまっているからだ。つまり、理解の及ばぬ不可解なものに貴重な人生を消費したくない、と数学的に計算してしまうからなのである。
ここで重要なのは、音楽の情報を得たとき、または得るときは、なるべく余計な雑念を打ち消しておくべきだということだ。邪念が入ってしまうと、根拠の無い未聴作品への否定が始まり、結局死ぬまでその音楽を聴かずに過ごすことになってしまう。それではあまりにももったいない。
トゥインクのような音楽は、決して万人が称賛するようなものではないが、それでも、まったく聴きもしないで軽蔑しているようなら、一度購入してじっくり聴いてみることを勧めたい。きっとあたらしい風景のうちの一つにはひっかかるだろうから…。
2005年12月24日
工藤冬里 「la consumption 4/atlantic city」
工藤さんの三日間連続講演が昨日、今日、明日とあるそうですが、仕事で一日も行けず…。
ひとまず、最近になって突如再発されたこの「アトランティックシティ」を聴いて我慢するしかないだろう。
工藤さんの絶妙なうたと、瞬間瞬間を生きる演奏がとても気持ちいい。
ここでは後のマヘルでの開放感とは違ったオープンな印象があり、それはもしかしたら窒息するような苦しみなのかもしれないけれど、工藤さんは閉塞感を一切感じさせない。
自由な表現、という言葉を耳、もしくは眼にすると、工藤さんの曲をいつも思い出す。
マヘルの曲「エヴァとマリアとジュリエット」が印象的なので引用してみたい。
とあるモーテルのさみしい家具の中に デスバレーの思い出を捨ててきたのだ
命の道か死の道か
エヴァかマリアかジュリエット 誰のために
一度外した足枷をまた着けるのか
今も同じ竜と闘って…
この「とあるモーテルのさみしい家具の中に」というフレーズがどういうわけか忘れられない。ことあるごとに頭の中にこの曲と工藤さんの声が響き渡る。なんという中毒性であろうか。
工藤冬里という巨大な才能が三日間連続で目の前で見れるというのに、私はチャンスを逃してしまった…。まだ、今夜と明日の公演は間に合う、誰か私の代わりにあの素晴らしいうたを聴いてきてほしい。今夜はクリスマス・イヴだ。こんなにぴったりのシチュエーションは、もうないかもしれない。
2005年11月08日
THE ZOMBIES 「ODESSEY AND ORACLE」
というわけでブリティッシュのゾンビーズ。
ソフト・サイケの大名盤ですが、「好きさ好きさ好きさ」が入っていないのでこちらのアルバムを最初に買う人というのは少ないですね。みんなベスト盤や編集盤を買おうとしますが、そんなことせずにまずこれを聴いてほしいです。
とにかくアルバム一枚通して素晴らしくポップだが、当時のイギリスでのゾンビーズの扱いは酷く、あまりパッとしないまま解散してしまったのである。当時はどちらかというと、どっぷりクスリに漬けたようなドロドロのへヴィサイケが登場してきた時代であり、このようなポップなソフトロックは飽きられてしまっていたらしい。
だが、ゾンビーズの影響を受けたバンドも多い筈で、このスタイルの無名ソフトサイケバンドはしばらく増殖していく。やはり捨てがたい魅力があったのだろう。
現在ではリマスターされ、ステレオ、モノラル、そしてボーナスまで入った紙ジャケのCDが再発されており、容易に入手可能である。
未体験ならばぜひ、このフラワーサイケに浸ってみてください。
2005年11月07日
ゾンビーズ
海外のあのバンドではなく、日本の80年代初頭に活動していた人達。
とにかく素晴らしいので勢いあまって紹介してしまったが、果たしてこれを知っている人がどれほどいるのだろうか?
まずA面の「ファイナル・ソング」における工藤冬里のピアノが美しすぎる。工藤氏のピアノはあまり聴ける音源が少ないのだが、ジャズを基調とした素晴らしいものであることだけは言っておきたい。
ヴォーカルはややポジパン風味というか、当時のあの系統のオルタナティブ・デカダン歌唱なのだが、ドラム・ベースはしっかりしたリズムをキープし、ギターも適度な暴れ具合で聴きやすい。ここまでのクオリティで他の作品が残っていないことが悔やまれる。
ひょっとしてこれ以外にも彼らの音源ってあるんでしょうか? 知っている方がいたらコメントお待ちしております。
2005年10月11日
Earthen Vessel
ジャケットに大きく「HARD ROCK」などと書かれているが、実態はガレージ系のファズ・サイケ。多分本人たちもハードロックの意味とか演奏法とかよくわからなかったんだと思います。ムチャな感じのファズギターがジャージャー鳴って、下手めの演奏が炸裂します。
ただ、オリジナル盤が異様に高いために知名度はそこそこあるバンドです。誤ってハードロックコーナーで激安販売されていたら即買いましょう。
一応CD化され、私もこうして聴いているわけですが、一体何人の人間が真剣にこのバンドをフェイバリットとして挙げるか、と考えると寂しい気持ちでいっぱいです。
下手にプレミアがついてしまっているレコードほど、CD再発されたときにあまり評価されていない気がしますが、どうなんでしょう…。
本作は71年作なのですが、音だけ聴くと60年代から抜け出せていないのが丸分かりで、更に奇怪なゴスペル風のコーラスがガンガンに絡むために正体不明の怪しさを醸し出しています。それでも、けっこう聴き続けていると耳に馴染んできてしまうのが恐ろしいです。
GANDALF
これがドリーミーサイケの代表格なのは、アルバム一枚通して同じ空気が流れているから。
GANDALFはNYのメロウなソフト・サイケだが、リリースはこの一枚のみ。それでもサイケを語る上で絶対に外すことの出来ないアルバムである。
とにかくオリジナル曲もカバー曲も、GANDALF特有のドリーミーサイケとして昇華されている。この独特のサウンド作りは異色であり、とにかく聴いて判断してもらいたいのだが、常軌を逸した変態サイケの世界がたっぷりと詰っている。
奇妙な空気感覚はサイケムーブメントの影響もあるのだろうが、それよりもこのバンドの先天的な変態性が素晴らしいのである。
本質的にはサイケだが、極めてナチュラルな酩酊感が他のバンドとの格差を生んでいるために、このアルバムは特殊なドリーミー・サイケの名盤として君臨している。
LAZY SMOKE 「CORRIDOR OF FACES」
68年Massachusetts産サイケデリアの傑作。
ジャケット裏にヴェルベット・アンダーグラウンド風味、みたいに書いてありますが、サウンド的には(というかボーカルの声質が)ジョン・レノンです。精神的な面ではヴェルベッツが保有していたサイケ感覚を持ち合わせているようでいて、表面ではポップ・サイケな香りがするという、いるようでいないタイプのグループです。
注目なのはCDのボーナスで収録されているアンプラグド音源で、ここでの演奏はサイケデリックと呼ぶに相応しい酩酊感に包まれていますね。
虚脱感に包まれた中で放たれるジョン・レノン風のボーカルがクセになるので、しばらくは封印しますが、薄暗い部屋で一人聴くにはぴったりの一枚です。
2005年09月26日
森田童子
透明な灰色が描きだす「ぼくたち」の風景は、感情の交流を拒絶している訳ではない。むしろ積極的にこちらへ手を差し伸べてくる断絶とでも言ったらよいのだろうか。うたの隙間からこぼれ出す不安や挫折は、全て偶発的な性質ではなく、意図的に作り出した感情であることが窺えるのだ。
自らが突き放した時代性を、感傷的ともいえる詩とあのアルペジオの旋律でくっきりと映し出す森田童子という象徴は決して失われるべきではない。ましてやテレビドラマの主題歌になど…と思ったのは私だけでは無い筈である。森田童子は神聖な場所として機能すべきだからだ。
ただし、森田童子は死を克服しているわけではない。死という最大の喪失に対して取るべき態度は一人の傍観者としてしっかりと見据えることだと彼女のうたは告げているように聴こえる。
これを聴いて青春のセンチメンタリズムだけを受け止めるのもいいかもしれない。だが、本質は喪失への断絶である。希望に似ているかもしれないが、どちらかというと希望のための諦念といった道のりが見えてくると思う。だからこそ彼女のうたは断じてニヒリズムの範疇に収まるべきものではないのである。ネガティブなイメージと空虚な気持ちを抱いたまま、それでも生き続けるという全ての人間の存在を、森田童子ははっきりと描写していたのだから。
2005年09月10日
RAINBOW FFOLLY
幻想で遊ぶことの面白さを知ってしまうと、ここにあるような総天然色のおもちゃが自然に出来上がる。明るく楽しく、健全なクスリ遊びの世界だ。ただ、他人がおおはしゃぎで遊んでいる様を見せつけられているようで少し不快になるという人にはオススメできない。
磁石の感覚、照りつける日差し、60年代サイケデリックの影。
本質が風景的であるが故に、SEは対して効果的に響いていないが、何も無いよりはあった方がいい、という考えで入れられているような感じである。そのおもちゃ感覚がポップサイケにとっては重要なものなのだが、40年近い歳月を隔ててしまうとそれが不気味に変質し、理解不能の「ヘンな音」になってしまう。
今現在、このような60年代のサイケを聴いて楽しめるのは、時間経過による我々の感受性の変化があったからだ。もし我々の感性が60年代のままなら、この盤を聴いても「当たり前の音楽」としか映らないのであり、古い時代の良さみたいなものを闇雲に模索したところで、それははかない幻想に過ぎなくなってしまう。
機材、時代、そして人間の考え方も僅かながら変わったのである。あまり音楽を時代の背景として捉えた発言はしたくないのだが、全ての再発盤を新譜として、買ったそのときがその音楽の最も旬な時期と認識して聴くという姿勢がなければ、あらぬ誤解を誘発したり、音楽そのものを無駄死にさせかねない。
そうならないためにも、私は「現在」を設定せず、再発盤も新譜として聴いている。そう、音楽には鮮度があって、せっかくイキのいいサイケでも「68年のアルバムだ」などという余計な予備知識があったせいで腐ったニオイを放つことだってあるのだ。それは受け手側のエゴなのだが、少しだけ聴き方を変えてやるだけで、全ての旧譜が「新しい音楽」へと生まれ変わるのだから、一度は試してもらいたい方法である。
音楽を一切知らない人にバッハを聴かせ、これがロックなんだと説明すれば、その人にとってのロックはバッハが基準点となる。つまり、最初の段階で「何も持たなければ」全ての音楽が新鮮な姿で甦るのである。
これほどまでにリーズナブルかつ単純な方法で、音楽鑑賞をより一層楽しむことができるのだ。一度聴いた音楽だって「忘れてしまえば」いい。そうすればCD一枚で一生楽しめるし、無駄な金を使わなくてもよくなるのである。
貧しい音楽好きはまず、いままで聴いた音楽を記憶から抹消すべきだ。
2005年08月06日
Jefferson Airplane
デビュー40周年。凄いですねぇ。こんなベストも出たし、そろそろジェファーソン・エアプレインも一般的に支持されてもいいんじゃないかと思うが、スペンサー・ドライデンが亡くなったというニュースがほとんど日本で騒がれていない現状を見ると、まだまだ鎖国的な性質が我が国にはあるのか、などと思ってしまう。
以前デッドのジェリー・ガルシアが急逝したときもそうだったのだが、ロックの偉人が死んだところで、俺たちには関係無い、というような態度を日本のメディアはとっているような気がする。何かの雑誌で故・隅田川乱一氏も指摘していたが、このままの状態だと、日本のロック界で死者がでても、報道機関はいっさい騒がないんだろうな、という不安を強く感じる。たとえば水谷孝や山口フジオが死んだところで、誰もその死を報道しようとしないだろう。本当は絶対的に報道すべき内容だと我々は考えるが、メディアの判断基準というものは曖昧かつ適当なものであるということを、スペンサー・ドライデンの死と、それを大々的に報道したアメリカのマスメディアは浮き彫りにしたのである。
2005年07月19日
DIP THE FLAG 「FROG MAN」
DIP THE FLAGの中ではこれが一番聴き応えのある作品だと思う。
やっぱり後のDIPとは全く違う音で、サイケデリック感覚はこちらの方が断然上。DIPになってからの轟音ギター的なアプローチも嫌いではないが、やはりこの時期の不可思議な感覚がDIP THE FLAGの持ち味としても最高峰だろう。
この路線でもっと作品を発表してもらいたかったのだが、本盤も既に廃盤となっており、DIP THE FLAG自体に触れることが難しい環境になってしまっているのが残念だ。
ライヴ盤の方もいいが、よりDIP THE FLAGらしさが出ているのはスタジオ録音の本作。整えられた音が歪んで聞こえるのは、彼らの狂気がダイレクトに封じ込められているからに違いない。
重要なバンドだと思うのだが、DIPより評価されていないような気がする。もっと取り上げられるべき魅力はあると思うのだが、なぜだろう?
2005年07月15日
T-REX 「cosmic dancer」

この曲はあまりにも霊的であり、サイケデリックをもう一層深く掘り下げた地点で、今も不気味に揺れ続けている。マーク・ボランというシャーマンがいかに本物であったかを語ったならばキリがないが、この曲を一曲だけ聴けば全て了解できるだろう。
宇宙は不定形だが、そこへ溶け込む我々は定形なのである。アルバム「電気の武者」が僕らに与えてくれた宇宙を、ゆっくりと傍観し、そしてその中へ泳いでいけば問題は無いのだ。
僕は古びたインチキメーカーのギターで、この曲を何度となく弾いた。意識しなくとも、自然とリバーブがかかったように聞こえ、アンプもエフェクターも通していない音が、極めて美しく転がっていくヴィジョンに何度も驚かされた。そこがマーク・ボランの墓場であり、誕生の瞬間でもあるという事を考慮しても、やはり楽曲そのものの霊性がこのサイケ感覚の根源なのだろう。
最近になって、T-REXのライヴ盤が出ていたが、どうにも聴く気になれないのは、かつてのアイドルを神棚の裏に隠蔽したくなるような庶民的な習慣が僕の身体に染み付いてしまっているからだ。まったく迷惑な慣性である。もう貧乏クサイことは言わないようにしていたのに…。
振り向くと、押入れに隠していた筈のマーク・ボランが、ゆっくりと笑っていた。
どうやら、初めから僕らは踊っていたようである。
2005年07月05日
頭士奈生樹 「PARADICE」
小人の魅せる深淵の風景は、現実的な要因での絶望や希望とはかけ離れている。ピグミーは幻想の中で生き続けるために、結界に似た呪術的防御網で自らの存在を守っているのだ。
頭士奈生樹という素晴らしい音楽家がいる。これは彼の1stアルバムであるが、以前にも最初期の非常階段やハレルヤズなどに参加していた。
そんな、アンダーグラウンドの世界では割と知られた存在のミュージシャンであるが、本作はアナログ限定500枚であったため、まだ聴いたことの無いという人たちの方が圧倒的に多いと思う。そんな中、つい最近になって突然彼の3枚目のアルバムが発表され、本作も同時にCDで再発された。私はオリジナル盤を持っていたが、もちろんCDも買った。そして最近は毎日聴いている。
頭士奈生樹の宇宙は限りなく幻想的であるし、彼のうたは限りなくやわらかい。深いギターサウンドが描き出す風景は、懐かしく美しい、見たことの無い場所なのである。
本盤のような秀作が理解されないならば、サイケデリックはもうおしまい。でも、ここにあるような素直な楽曲ほど、評価されにくいものなのかもしれない。純度の高い物質ほど、周りに与える影響は多大なのだから。
2005年07月03日
宮沢正一 「キリストは馬小屋で生まれた」
決定までのプロセスに特定の意思が介入してしまうと、それは本当の意味で決定などしていないと言える。意思は介入しただけであるが、こういう場合においては本質となる。
キリストがどこで生まれ、どこで死んだか。
それは、その問題を考える人間の数だけの解答が用意されているのだ。
だから、竹内文書と戸来村の関係およびキリストが日本で死んでいたという説を目の前に提示されたところで「へぇ」とか「ふーん」としか答えられない。竹内巨麿の作り出した妄想だ、といって糾弾してもいいし、キリストの墓参りに青森県へ旅立つのも不正解ではないだろう。
宮沢正一のうたは、メルヘンと現実を同質のものとして溶解させてしまう。このソノシートのA面「キリストは馬小屋で生まれた」にしろ、「ぼく」というのはどういう人物なのか? ということに関しての余計な説明は一切していない。この隠蔽の技術によって、奇妙な恐怖に似た感覚が聴き手を襲う。
アシッドフォーク、と一言で済ませてしまうには、あまりにも深すぎる内容なので、機会があれば一聴してほしい。再発されたCDも現在では廃盤なのだが、根気良く中古店をまわったとしてもこれは聴くべき、そして聴かれるべき一枚である。
2005年06月24日
真島昌利 「夏のぬけがら」
ブレイカーズのテープにカビが生えて捨てざるを得なくなった。
当時、僕の住んでいた部屋はやたらと湿度が高く、畳も箪笥の表面にすらも、うっすらとカビが発生していた。そのせいでずいぶんとたくさんのビデオテープやカセットテープ、機材が使い物にならなくなってしまったのだ。被害は深刻で、カビの力って恐ろしいなぁ、などと言ってられるほど穏やかな状況でもなかったのである。
真島昌利といえばザ・ブレイカーズ。最高にカッコいい、イカシたビートバンド。そんなブレイカーズのテープがダメになって、僕はそれ以来マーシーの曲を聴いていなかった。
本作「夏のぬけがら」はブレイカーズ時代の名曲「アンダルシアに憧れて」も収録されていることで有名だが、真島昌利という人の優れた作曲センスにまず驚かされる。ゆったりとしたサイケデリックな楽曲と、マーシーの枯れた歌声は絶品であり、ブルーハーツともブレイカーズとも違う景色を描いている。
面白いのは、友部正人の曲をマーシーが歌って、ここまでピッタリと合った雰囲気を作り出していることだろう。
この「夏のぬけがら」はゆったりとした郷愁感覚と、真島昌利本来の音楽性が剥き出しになった傑作である。ブルーハーツよりも、僕はここでの彼が好きだ。とびきり素直でそのままの楽曲に、彼の飾らないボーカルが乗っかることによって、ブルーハーツとは違う青春が顔を出している。
2005年06月16日
DIP 「TIME ACID NO CRY AIR」
魂ぬかれる。
これ、意外に思われるかもしれないけど、DIPの中で一番好きなアルバムだったりする。もちろんディップ・ザ・フラッグとヤマジカズヒデのソロは別物としてだけど。
スーパー・ラヴァーズ・イン・ザ・サンの、あの歌謡メロディと歪んだギターの調和は素晴らしい発見であると同時に、太古より脈々と流れてきたロックのスピリッツをきちんと踏襲している。DIPもついにここまで来たかぁ、と随分納得したものである。
この少し乾いた感覚のアルバムの後に『WEEKENDER』でまた深い混沌のサイケサウンドを打ち出すわけなのだが、個人的にはここでのポップかつソリッドな演奏がベスト。
最近のDIPも好きだけど、この中期の雑多な感じは、見過ごすにはもったいない魅力を秘めている。
轟音ギター盤として話題に上る事の多い本作だが、DIPの魅力は曲作りそのものにあるので、轟音だけのために本作を聴くのはあまりにももったいなさ過ぎる。
と、さっきからもったいないもったいないと繰り返しているが、DIPの楽曲にはおびただしい量の情報が含まれているので、もったいなさを感じる人間にとってもかなり満足できる仕上がりになっている。
1枚で5枚分は楽しめる充実盤。
2005年04月20日
ふきのとう
「白い冬」のジャパニーズ・サイケっぷりはもはや伝説ですが、他の曲も聴いてください。これはマジにクレイジーです。
ふきのとう、というグループはいわゆる「軟派なフォーク」として当時の硬派な人たちには忌み嫌われていましたが、今現在ここに詰め込まれた音と真剣に対峙してみると、そのあまりにも純度の高い楽曲に驚き慄くはずです。やたら透明な声とシンプルな演奏は、サイケデリックの構造を無意識に構築してしまっているのです。
まったく畏怖すべき名盤ですが、この前ちょっと欲しくなってタワレコを探したけど、一枚も置いてませんでした。合掌。
2005年03月25日
kudo tori-kinutapan-yumbo/igloo3~地続きの島を恐れるな
工藤冬里、真剣に好きなんですよ。大ファンです。
あのよれよれした調子っ外れな歌や、楽曲の構成を無視したギターとか、やたらにキレイなピアノも全て素晴らしい。
で、これはそんな冬里氏とkinutapan、yumboといったバンドが共演する好盤。聴いてないというなら、まだ普通に売ってるので今のうちに買っておいた方がいい。
一曲目からして凄まじい異世界が口をあけているが、冬里ファンなら「その後のLuo na」で絶対泣きますね、絶対。冬里さんのうたには誰も追いつけません。
以前、友人が井の頭線内で工藤夫妻を目撃し、そのときの冬里氏のスニーカーにはマジックで「レッドクレイオラ」と書かれていたそうな。なんとも心温まるエピソードである。
工藤冬里音源はブートばっかなので、そろそろどこかのレーベルが責任持って正式にリリースした方がいい。ちなみに某氏が出したCD-Rセット「TAPES」は僕のプレイヤー、及びPCでは読み込めないというとんでもない不良品で最悪(しかもなぜかディスク3だけ聴けない)だから買わなくても平気。ブートで買うならクラゲイルのスイートインスピレーションズが一番無難です。
2005年03月16日
オフコース 「I LOVE YOU」
2005年03月14日
Fresh blueberry pancake
2005年03月11日
クイックシルバー・メッセンジャー・サービス
2005年03月10日
FREEBORNE
2005年03月07日
Red Crayora 「The Parable Of The Arable Land」
サイケデリックは妥協してはならない。
正しい陶酔は秩序だってはならないし、諦念を少しでも感じてしまったらもうアウト。まがい物のレッテルを貼られて無様に漂うだけである。
レッド・クレイオラのこの音楽は、サイケデリックであることを一身に背負い込んだ本物の演奏であり、わずかな隙間から見える真実さえも極彩色に歪めてしまう、マジカルな儀式だと言える。
なぜ民俗学者はこのような音を問題にしないのか?
儀式的なもの、宗教の起源として横たわっている人間の根底にある感覚を無造作につかみ、引っ張り出そうとするのがメイヨ・トンプソンの技法である。だからここにある演奏に飲み込まれてはならない。心地よい陶酔が悪夢へと一変してしまわないように、われわれは細心の注意をはらってコレに接しなければならないのである。
恐怖と驚きと、始まりを形作るための第一歩。
2005年03月05日
The Hollies 「Evolution」
昨年くらいから突如再評価され始めたホリーズ。何でいまさらなのか知らないが、多分CMか何かで流れたんでしょう。
これは彼らの一番サイケな6枚目。ジャケットからしてポップサイケな香りが漂ってますね。
さて、2分30秒の中でどれだけポップでドラマティックな曲を構成できるだろう?
限られた時間軸の中で魔的なからくりを封じ込めていく手法は、このホリーズの専売特許である。限りなくポップでキャッチー。そんな2分30秒平均の曲を連発するバンドだったホリーズが、いままで全然と言っていいほど評価されていなかったのが不思議である。
紙ジャケで日本盤も出ているので、すぐ聴けるようになった感動の名盤。ただモノラルとステレオの同じ曲を一枚のCDで通して聴くのは辛いかもしれないけどね。
2005年03月03日
summer sounds up←→down
2005年02月26日
JA シーザーの世界
シーザーの本です。これがヤバイのは付録のCDに入ってる音源が強烈だから。
それにしても「シーザーと悪魔の家」って、北欧のブラックメタルみたいな感じのステージ写真ですね。日本を代表するへヴィ・サイケとしてシーザーの名を出さないのはもったいないし、ここになんとなく入れられた楽曲は音質は悪いがサイケ具合は満点。こういうハードロック調のサイケって日本では珍しいよね。他に似た感触のバンドはマキオズくらいかな。
シーザーの曲って、演奏もうまいし大袈裟にやるもんだから一部ではかなり評判良かったと思う。ただ寺山先生の関係だから、どうしても演劇のワクを外して見ることができなかったんでしょう。当時にきちんと評価されていたら、今の日本のサイケもちょっとは変わってたかもしれませんね。
2005年02月22日
Manuel Göttsching E2-E4
2005年02月19日
ガセネタ 「Sooner or Later」
宇宙人の春がタコのB面最後に入ってて、やたらと掻き毟るようなギターがカッコいいな、などと思っていたら、どこから見つけたのかガセネタの現存する音源を集めたアルバムが出た。
って、何年前の話だろう。いまさらな感じもあるが、ガセネタの音は古くないよ。というよりむしろ今こそ若いサイケデリック・スピード・フリークスな連中はこれを聴いて本物の凄みを味わってほしい。
あ、と思っても遅いし、浜野純のモズライトのギターは闇の中から突然切りつけてくる卑怯で怖いもの。前にだれか(連続射殺魔かな)が「シド・バレットの目をしたブースカ」と浜野を形容していたが、当時のハルミの外見もそんな感じだし、このバンドこそ「シド・バレットの目をしたブースカ」なのかもしれない。
2005年02月12日
五つの赤い風船 「おとぎばなし」
AMON DUUL Psychedelic underground
頭の中では困惑しているのに笑顔。
ごまかしはそこにあって、ぐるぐると回る土台の上で思考を続けながら現状を維持している。
迷惑な騒音。美しい旋律。吐き気がするような音波。懐かしいフレーズ。
それらすべてがまやかしだったんだ!
うれしくなって北東の窓を開けても、神様はやってこないのであって、徹底的に打ちのめされた夕暮れの空気がゆったりと流れていく。
キラキラと水色に光る、水に関係した映像を欠伸を堪えながら長時間見ているような気だるさ。それが正義であり、常識なのである。
サイケデリックアンダーグラウンド。ここから来て、どこへ行く?
井上陽水 「少年時代」
これぞサイケデリック! ジャパニーズ・サイケの重鎮である陽水先生が突如発表したリヴァーブかけまくりの完璧にイッちゃってるシングル。これは誰にも批評できないだろう。
こういう危なっかしい曲を普通にメジャーからシングルで出して、なおかつヒットさせるんだからやはりあのアフロは伊達や酔狂ではなかったのだろう。ピアノもストリングスも、全部リヴァーブが掛かっていて、もはや異次元の楽曲。すげぇよ、これ。
少年時代というタイトルから覗えるノスタルジーは一切無く、ただただ深く酩酊するトリップ感覚に支配されている。陽水はここへ来てまだシャーマンとしての実力を失っていなかったのである。
2005年02月11日
hunt&turner 「MAGIC LANDSCAPE」
2005年02月09日
Maher Shalal Hash Baz 「今日のブルース」
1日に一度はそれを食べないと、身体がおかしくなってしまう。自動的に爆発するならまだしも、数学的な原因を持たずに変形、拡大を続けていくのだから困ったものである。
と、複数の「ヒト・もしくは人」が囁くので、堪り兼ねて落下するというのも気がひける。だから今日のブルースは明日のブルースまで辿り着く前に昨日のブルースとして機能のブルース。有機的だなぁ。
バクーニンを非難する前にマルクスを疑えと枕元で紫の怪人に説教されたような気分になる。そんな工藤冬里の声はどこから響いているのだろう? ヴェルベッツもラリーズも、ここまで純粋にはなれなかったし、それを考えると、マヘル・シャラル・ハッシュ・バズほど呪われた音楽も珍しい。
個人的にマヘルから受けた影響は絶大である。
2005年02月07日
CA QUINTET
昔デパートの屋上にあったアーケードゲーム「魔界村」を思い出すジャケだが、中身はクスリ漬けのマカロニ・ウエスタンといった感じ。一応サイケの名盤ですけど、いままで出てたブートは全て音質が最悪だったり曲数が変だったりするので、サンデイズドから出てるCD以外買わない方がいいです。オリジナル盤なんて何万もの値がついてるし、サイケマニアのせいで良い音楽がどんどん手の届かない場所へ行ってしまうという現状が呪わしい。
サイケのサは差別のサ、サイケのイは異物のイ、そしてケは貶してくださいという自虐の心。みんな悩んで大きくなったと勘違いする野坂の亡霊が見える。
2005年02月02日
HOPE SANDOVAL & THE WARM INVENTIONS
近年稀に見るアシッドフォーク。ホープ・サンドヴァルはマジー・スターでおなじみだとして、ワームインベンションズって何? と思った人多いと思います。これはメンバーが曲ごとにバラバラで、全曲やっているのは元(?)マイブラのドラムだけという企画モノ色の強いユニットみたいです。
まぁ、ホープ・サンドヴァルのエコー声が聴ければそれだけで満足な僕などにとっては内容なんて無くてもいいようなものなんですが、クオリティはやたら高いです。何も知らない人に「68年のアシッドフォークだ」と言っても疑わないでしょう。シンプルに美しく、そんなありがちなキャッチコピーで充分語れる普遍的名作。頭がとれたら代わりを探すという屍の気持ちと、死後の世界がありがちなミスで無くなってしまうことのどうしようもなさを的確に指摘する音楽。
2005年01月31日
Silver Apples 「コンタクト」
銀の林檎は変な音を出すことで有名だった。自分だけの音楽、自分だけの宇宙。そんなものを設置するためだけに、銀の林檎は我を忘れて電子音を発し、歌う。宇宙船が満員になっていることに気付いてなかったのは、彼らが最初から一人としてのスペースしか所有していなかったからだ。だから、誰のせいでもない。
システムを構築することがここまで容易かつ軽はずみな気持ちで可能だということに、賛同するような真似はしたくないし、歴史のような広大な地平から見て彼らを語りたくもない。だから、いつしか銀の林檎は忘れ去られてしまうだろう。そのときに誰かがこの音楽を思い出せば、また空間が幾つもねじれていくのである。
2005年01月27日
ハレルヤズ 「肉を喰らひて誓ひをたてよ」
ここのところハード・コアばっかだったんで、たまにはポップ・サイケで。
このハレルヤズのアルバムに何度いい気分にさせられたことか。
ぎこちないうた、溶けるようなギター。
サイケってこういう感覚なんですね。もっと評価されてもいいのに、と思っていたらいつの間にか渚にてで柴山氏が復活。それに伴ってこのアルバムも結構売れ、うたものなどという単語で語られるようにまでなったわけです。
肝心なのは高山"Idiot"謙一や頭士奈生樹といった重要人物がゲストとして参加している点。こんな豪華メンバーで、しかも一番デリケートに音が露出する即興に近いスタイルで録音されているのだから、収録曲のクオリティの高さは聴かずともわかるでしょう。
本当に名盤だと思います。これ無しで日本語のうたは語れません。と、断言。
2005年01月20日
割礼 「ゆれつづける」
言霊が警報のように一定の高さで鳴り響いた時、呼び起こされるのは純朴な心であって、忌まわしい観念は付随してこない。定説とされているものとは明らかに相違する事象に遭遇し、慌てふためくよりも不思議と落ち着いた気持ちになれるというのは、我々が常にゆれつづけるからである。
シーンと静まり返ったライブハウスで、宍戸幸司はゆっくりと歌う。その歌はよく聴くと、物凄く普通の日常的な歌詞なのであるが、うたとして発せられたときに突如として会場がサイケデリックに歪む。
そして、あのギターである。他のサイケバンドのように極端に歪ませたり、リヴァーブをやたらとかけたりといった装飾が、割礼にはまるで無い。飾らないのでは無く、飾れないのだ。割礼の演奏にはまったく無駄が無く、極限までそのままの状態を保持し続ける。
ゆらめくような割礼の、これはメジャーから出したアルバムであるが、個人的には最高傑作としておきたい。ラストの唐突に終わる「ごめんね女の子」を聴くと、日本語サイケの亡骸が浮かび上がってくるのだが、下北沢のライブハウスで見た宍戸幸司の存在感は確実に現在を生きていた。
2005年01月13日
CHOCOLATE WATCH BAND 「The Inner Mystique」
チョコレート・ウォッチ・バンドという変な名前だけで、このレコードを買う価値はあります。A面はスタジオミュージシャンとか別のバンドとかで、ほとんどオリジナルのウォッチバンドは聴けないんですが、B面は必聴。なんせTHE BROGUESの名曲「I Ain't No Miracle Worker」をカヴァーしてる! しかもオリジナルの方よりカッコいいのだからたまりません。ウォッチバンドはサンデイズドから全部再発されてたと思うので、簡単に手に入れることが可能だし、たまにはこういうのを聴くっていうのも新しい発見があっていいんじゃないかな。
2005年01月11日
たま 「しおしお」
たまほどナチュラルに歪んだバンドもないだろう。このナゴムから出したメジャーデビュー寸前作も、曲目はメジャー盤1stとかぶるものの、内容的にはより畸形的。
まぁ、メジャー盤だけでいいって言うならいいけど、滝本晃司作曲の超サイケな名曲「夏の前日」を聴くためだけにこれを買うというのもいいですね。今はもう廃盤らしいですけど、根気良く探せばまだあるっぽいんで、ぜひ一度試してみては? ちなみに後の「いなくていい人」とかもかなりヤバイ名盤なので、たまは全アルバム押さえておきたいところですね。
このバンドの魅力は石川浩司(ランニングの人)にあると思う。彼の曲のセンスはかなり屈折してるし、歌詞もナチュラルに狂ってる。「学校にまにあわない 」のような奇怪な歌は、たま解散の今となっては孤高の存在である。
2004年12月29日
AMBOY DUKES
何故だか思い出せないけれど、以前知人が突然宮沢りえの「サンタフェ」をくれた。引越しのどさくさに紛れてそれは紛失してしまったのだけれど、その写真集をなんとなく見ながら、このAMBOY DUKESの1stをよく聴いた。
テッド・ニュージェントのギターが聴きたいのなら、ソロや他のアルバムでもいいが、AMBOY DUKESというガチガチの基本サイケをまず押さえるならここから。とはいえ、サイケというよりもブルース風ハードロックと言った方がイメージし易いかもしれない。
ハードロックのファンって意外と少なく、そのダサさというか、田舎臭さに耐え切れる人間が年々減ってきているような気がする。子供の頃はみんなツェッペリンだとかディープ・パープルだとか言ってるのに、中学へ入った頃から急にメタルだのパンクだのと言ってカッコつけるというのが現代の児童心理。そのまま大人になって、こういうのを聴き直すのもいいが、できれば多感な学生時代に聴いておきたいアルバムである。ちなみにオリジナル盤はバカ高。
LINDA PERHACS

落ち着きたいと思ってもなぜか立て続けに用事が重なってしまい、休む暇がどんどん削られていく。それでも休日はのんびりとどこかへ行きたいという現代人にオススメ。
これ、ハワイの女性シンガーのアルバムなんですが、やたらと完成度高いです。質感としてはサイケというよりカントリー。だけど透き通った声とサウンドの裏側にあるものは、万華鏡のように変化し続ける天然サイケデリック模様。いままであんまり評価されてなかったのはただ単に認知度が低かったからか。ちなみに現在ではCDで簡単に入手可能。やすらぎと酩酊をミックスせず、敢えて別々に提示しているような斬新さにため息。