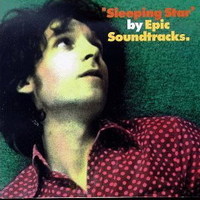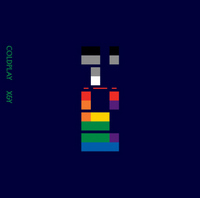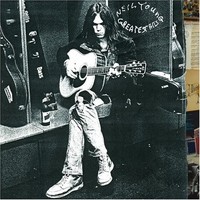凝解、その後 書き手・森本
世の中の右と左そしてうしろ 暗がりで笑う人をみたときや 銀行のATMで現金を取り忘れたときに なんとなく読むブログ
カテゴリー:ロック
2007年04月04日
Sonic's Rendezvous Band 「Strikes Like Lighting, Live 1978/79」
SRBのボックスが発売されたが、その六枚よりも激しいのはこの「Strikes Like Lighting」。
ボックスを凌駕するブート盤なんてこれぐらいのものだろう。
オリジナルは私も持ってないので、ダビングしてもらった「CITY SLANG」が途中で切れる音源でしか聞くことができないが、それでもこれは最高である。
SRBの激しさは多分この一枚に全て入っているし、割れた音質とややピッチの違う感じも荒々しくて気持ちがいい。こんなにカッコいいロックアルバムは滅多に無いと思う。
フレッド・スミスのギターがバキバキに鳴るこの音楽を聴いてなんとも思わない、という人とは友達になれそうもない。それぐらい桁違いのロックンロール。
ブログECHOES2007のTKさんも書いていた通り、ロックの本質が見えてきて、ジャンルやら音楽性なんてどうでもよくなる。これは紛れもない、本物のロックだと思う。
また、とげとげしい危険な肌触りがクールでもある。SRBというバンドの不良の香りみたいな雰囲気はさすがデトロイトだなぁ、とは思うんだけど、それ以前にロックって本来こういうものだったよね! という久しぶりの感動みたいなものが襲ってくる演奏が心を躍らせてくれる。
ボックスも出たのだから、このブートもまたCD化されてもいいんじゃないかと思う。
すべてのロック好き、ロックンローラー、ロックマニアは必ず聴くべきバンドである。
2007年03月31日
Elliott Smith 「Figure 8」
エリオット・スミスは2003年に、胸に刃物をつきたてて亡くなった。
死に理由を求めるのはよくないことだが、彼の死はショッキングであった。
恐ろしいぐらいに美しいソングライティングのセンスは、エリオット・スミスのアルバムをどれか一枚聴いてみればすぐに体験できる。特にこのアルバムはまとまっており、私は繰り返し何度も聴いた。あれは2000年のことだ。
アビーロードスタジオでの録音ということもあり、ポール・マッカートニーを思わせるメロディも随所に見受けられるが、エリオットのメロウな感覚はやはりオリジナルである。
暗くてドラッギーな世界を描いていたエリオットであるが、それらは全て身近な要素だけで構成されており、自らの内面からずるずると引きずり出される。
近年稀に見る存在感のsswだっただけに、やはりその死は喪失であった。
最近になって、またエリオットの未発表曲集『New Moon』が発売されるらしいが、なんだか聴くのが躊躇われる。
彼もまた、伝説になってしまうのだろうか?
2007年03月30日
ライカスパイダー 「ライカスパイダー'88-'89」
2007年03月20日
EPIC SOUNDTRACKS 「Sleeping Star」
2007年01月25日
Jonathan Richman 「I, Jonathan」
このアルバムの突き抜けたマイペースさ、それまでの実験精神すら放棄したかのようなほのぼの具合はきわめて霊的である。
一曲目、「Parties in the U.S.A.」からいきなりのんびりした情景が飛び出し、隠れた名曲「You Can't Talk to the Dude」なんかも痺れるロック具合。ロックが本来あるべき素の状態をそのままポン、と出している。
名曲も多く、聴けば聴くほどに味の出る好盤であるものの、あまり話題に出ない一枚なのは、ジョナサンリッチマンの本質部分が本当はどこにも無いんじゃないのか、という恐怖が無意識に働くからであって、決してそのロックンロールが虚像だからではない。
ジョナサンの曲が底抜けに「ジョナサン・リッチマンの曲」であらんとするようなインパクトを保持しているように聴こえるのは、しっかりとした芯のような本質が存在しているからであって、一見奔放に放出されているようなサウンドも、しっかりとジョナサンの精神を孕んでいるものだということを認識してから聴きたい。
ここで聴けるジョナサンの歌はあまりにも剥き出しで、時に恐怖すら覚えるが、そうでなくてはロックンロールなんて意味が無いのかもしれない。
2007年01月06日
BOaT 「RORO」
遅ればせながら明けましておめでとうございます。
今年もゆっくりやっていこうと思っています。
現在、オークションで1万円以上するという本作も、数年前は下北あたりで中古盤が500~1000円で買えた。今でも、ブックオフあたりなら間違えて安売りされている可能性もありそうだが…。
発売当時、すでにいろいろと評判を聞いていたし1000円でお釣りがくる金額だったために買ってみたけれど、どういうわけか全然聴かずにそのまま奥底へしまいこんでしまっていた。
今回、とある方から本作のことを書いてほしいとリクエストをいただいたので、久しぶりに引っ張り出し、改めてプレイヤーにセットした。
デジタルな音で行われるサイケデリックな演奏。と書くと誤解されそうだが、当初の印象はそんな感じであった。極めて現代的な、2000年代のポップ・プログレかな、なんて軽く考えていたわけだ。だからこそろくに聴かずに実家の奥底へ封印されてしまっていたのだけれども…。
ところが、今回聴き直してみてびっくり。深いし、はじめて聴いたときのデジタルなイメージはまったく無かった。どうやら数年前の自分は耳やアタマがおかしかったようだ。
BOaTというバンドについては、ここに経歴やらメンバーに関してを書くのはやめておく。余計なデータは知らないまま、音に接した方が私のように妙な印象を抱いたまま封印するようなことは回避できるだろうから。
本作の緻密な音の動きは、同時にポップなメロディも抱き込んでおり、サイケデリックに似たゆったりした酩酊感を提供している。
黒、と来たらすぐに緑を。赤、ときたら黄を。という具合に、識別した瞬間に別の回答が投げられるような感覚が延々と続いていて、なおかつリラックスできるような仕組みである。
忙しいのにゆったりできる。一見矛盾しているようだが、心地良いスポーツのあとのような感じを想像してもらえば伝わるかもしれない。この音楽は、未来的でも無ければ、古のサイケデリックでもない。ただひたすら現代的であり続けることの美しさを、演奏として残している大傑作であるのだ。
できればライブを見てみたかったというのはあるが、これ一枚あればもう自分は満足だ。
かつてのフリージャズ、かつてのロックンロール、かつてのサイケ、それらの名演と同じ位置に立てるだけの存在感を今出すには、徹底的に現在の音楽、演奏であることを誇示すれば良いのである。過去の模倣や真似ごとではなく、現代的であることを選択した彼らに、私は拍手を送りたい。
ただ、私は気づくのが遅かったわけだが…。
2006年11月06日
NICO 「Chelsea Girl」
この人が重要なのは、ドラッグの香りを死ぬまで纏っていたから。
そして幸薄そうな佇まいとあの声が、薄暗いホンモノのドラッグ・カルチャーをしっかりと伝えてくれる。
VUもののブートが続々流出していく中、NICOのブートもそろそろ決定版が出されるのではないかと期待しているのだが、どうだろう? 時期的に出そうな感じはあるんですけどね。。
ひとまず、この名盤を聴いてないという人は、家にあるほかのレコードを売り飛ばして買いましょう。
それぐらい良い一枚です。
NICOについては書きたいことが多すぎるので、あえて書きません。
このレコード一枚にどれだけどっぷりはまったことか。。。
罪作りな一枚です。
2006年11月02日
THE SLUDGE 「The Brain Kept A Rollin' 」
80年代のロック界において、最後のカルトアイドルになっていた、ザ・スラッヂ。
なぜか音源が出ない。中古レコードは売っていない。活動は20年近くストップ。
そんな状況の中、突然のCD発売がなされた。
まさかここまで音源が残っているとは思わなかったし、CDが出るなんて夢にも思っていなかった。
それがこうして目の前に形になってみると、なんだか不思議な気分だ。
後期(1985-1987年)の未発表ライブ音源がこのCDには80分近く収録されている。
皆が期待しているあのギターの音や、捩れた迫力のボーカル、図太くうねるベース、タイトで通好みのドラムがたっぷり聴けるのである。
ロックであることのオリジナリティは充分すぎるほど発揮していたバンドだけに、まとめて聴くと重度のめまいがする。一般のロックファンが通過してしまっても、そのうちの何人かは確実に立ち止まって耳を傾ける魅力が、ここにある演奏には満ちているのだ。
このアルバムは決して再発ではない。
すべて未発表の音源だけを集めた、いわば新譜なのである。だからこそ、新しい耳で、今の音楽好きが聴いて思う存分に影響を受けて欲しいと思う。
また、当時を思い出して聴くのも再発見に繋がる良いきっかけとなるだろう。ここにある音は20年前の演奏だけれど、時代に取り込まれなかった異分子なのである。だからこそ、ここまで新鮮に響くのだと思う。
まだ流通のルートが限られているようだが、もっと多くの人に届けられれば、確実に意義のあるリリースになると私は思っている。
根底にあるロックのグルーブ感、踊りだしたくなる強烈な演奏。ザ・スラッヂはまだまだ転がり続けているのである。
2006年10月12日
THE ONLY ONES
ピーター・ペレットの声は、ドラッグ漬けのあの感覚を思い起こさせる。だが、それと同時にポップで普遍的なメロディがしっかりと鳴り響き、まるでルー・リードのようなペレットの歌唱も独特の憂いを纏いながら上昇していく。
ペレットは一時ドラッグで再起不能だとか、廃人になっているとか、死亡説までながれていたが、突如復活を遂げ、ライヴを行い、ライヴ盤のリリースも行っている。そこからまたドラッグへ、という話もあるが、ペレットの音楽がドラッグの影響無く鳴り響いていたことが、あの復活の演奏からは感じられる。
「Out There In The Night」の日常風景がゆったりとただ流れていくような美しさや、「Another Girl,Another Planet」のドラッグソングでありながら現実に根付いたロマンティシズムを展開させる手法はあまりにも眩しく、ペレットのソングライティングの良さには脱帽する。
画像はオンリー・ワンズ時代の、ベスト盤で、安価かつ入門には良い内容なのでこれからペレットの世界を覗く人にはオススメしたい。
オンリーワンズを全て聴き終わったら、今度はペレットのライヴ盤を聴いてほしい。魂の美しさがひねくれた性質をも明るく照らしてくれる。
2006年09月14日
LIBIDO 「RYU-SA」
成田弥宇氏は、自らの立ち位置をしっかりと把握し、実直な姿勢でLIBIDOという一つのシステムを動かしていたのだと思う。生きていることのリアリティ、音楽表現ということへの可能性。成田氏の地を引きずるような陰鬱なサウンドは、表面的には暗黒が広がっているように見えるかもしれないが、奥底でしっかりとそれらを纏っているものが確実な「生」のリアリズムだったことが、リビドーの世界を支持する者がいまだに多いということの解答なのかもしれない。
本作「RYU-SA」もまた、リビドーというバンドの美しさを知るには良い一枚である。
例によって、何にも似ていない、独自の音楽がリビドーのサウンドとして息づいている。ファーストよりも演奏、音質ともにまとまりがあるため、作品としてクオリティの高いアルバムである。
ロック、サイケ、ポジパン、プログレ、民族音楽などのエッセンスは多分に吸い込んではいるが、それらを外に出す際に成田弥宇という呪術師のフィルターがかけられている。そして、それは確固たるリビドーのオトなのであり、何かと比較することは明らかに無駄な行為でしかなりえなくなる。
29歳の若さで亡くなった成田氏であるが、いまだにその魅力に触発されて「リビドーのような音」に憧れるバンドは多数存在している。それだけ、あの輝きは絶大だったのだ。
2006年05月24日
Small Faces
2006年04月05日
Kevin Ayers 「RainbowTakeaway」
9作目。地味だが、明るくクールな演奏が最高なケヴィン・エアーズの隠れた名作。
この裏ジャケットの虹がすごく好きだ。
歌詞も素直で良いし、なんだか聴いていて気持ちのいい一枚である。
表のジャケットもなかなか味があり、ジャケだけ知ってる、という人も多いのではないだろうか?
スラップハッピーのアンソニームーアがプロデュースなので、スラップハッピーファンにも聴いてほしい一枚である。
このアルバムが出た78年、パンク・ニューウェーヴの真っ盛りにこのゆったりとしたAOR風のサウンドが評価されなかったのは当然なのかもしれない。
自宅でゆったりと聞くにはちょうどいいアルバムだと思う。お気に入りのワインなんかを飲みながら…。
2006年03月23日
Jackson Browne
初期ジャクソン・ブラウンの良さは歌詞にあるとよく言われているが、本当は三作目までのあの霊的なアコースティック・サウンドがそれを引き立てていたことはあまり語られないでいる。
一枚目ではもっともストレートな形でジャクソン・ブラウンという男の世界が表現されているが、あの質感の完璧さや、生活感の溢れる空気を社会的なステージを意識させる歌詞を前にすると、思わずため息が漏れる。
やはり彼の世界は地に足の着いた理想を引き寄せるような、広く一般的すぎる努力の過程をドラマティックに構成しているようにも思える。
ここで薄汚い政治性を持ち出さなかったのは、やはり彼が詩人であり、フィクションの中での作業を望んでいたからだと思うし、あの不思議な土の匂いが混ざったサウンドを耳にすると、その心地よい世界にしばらく滞在したくなる欲求にも駆られる。
後の彼はバンドサウンドを強化してしまい、初期の頃にあったような美しい風景は描かなくなってしまった。それはLate For The Skyで涙した我々にとっては大きな喪失である。
久し振りに彼の一枚目を聴きなおすと、忘れていた風景がふいに思い起こされたりして、なんだか切なくなる。
2006年03月22日
大江慎也 「THE GREATEST MUSIC」
メンバーは大江、花田、井上、池畑の4人、まさに初期ルースターズの復活盤とも言える究極の一枚である。
ここまで完全な、理想的ともいえる復活を遂げるとは、UNの時点ではまったく思いもしなかった。
楽曲は参加メンバーから分かるように、ルースターズ初期の「あの」感じである。懐かしくもあるが、極めて現代的とも言えるこのアルバムは、あまりにも素直であるが故にその素直さの絶対性を定義づけてしまっている。
というわけで、ルースターズを知らない者にとってはここにある素直さ、ストレートさが異様なものとして映る可能性も否定できない。なるべくなら、大江慎也という人物の過去の音源や経歴を踏まえてから本作を聴いたほうが、妙な誤解は抱かなくて済むと思う。
まずはPVでの動き回る大江を見てもらえれば、このアルバムへの気合いがいかなるものかがよく理解できると思う。
本物のロックンロールが、また楽しめるのである。
2006年03月16日
COLDPLAY 「X&Y」
静寂の中で蠢くメロディは、はっとするぐらい美しい瞬間がある。
コールドプレイのこのアルバムは、異常なまでの緊張感と神経すべてが麻痺するような美しさに満ちている。さすがに冬場は体温を奪われそうでそんなに聴かなかったのだが、気候が春めいてきたので久し振りにプレイヤーにセットしてみた。
「Speed Of Sound」の繊細さと沈み込むような感覚は異様である。ここまでのものはそうそう出てくる音ではないし、コールドプレイが頭一つ抜けたセンスを持っていることはこの楽曲を聴いたことのあるものならば理解できると思う。
ただ、明らかに癒しの音楽ではないので、病床に伏しているときなんかは聴かない方がいい。取り殺される危険性もまた魅力だと言えるのかもしれないが…。
2006年03月03日
人間クラブ
南浩二のロックスターぶりには誰もかなわない。後に大江によってあそこまで完成されたバンドになったルースターズであるが、この人間クラブの時点では南のアクの強さが前面に出ており、当時の北九州にこんなバンドがあった、という事実以上のインパクトをこの残された音源から感じ取れる。
南のヴォーカルスタイルはサンハウスの菊にそっくりであるが、やはりロックンロールしているという点では誰も否定できるものではない。
楽曲は村八分などのパクリっぽいものであるが、これは大江が村八分ファンであったからであり、盗作なんかではなく愛のこもったオマージュといった感じだ。サンハウスの「レモンティー」もそうだが、九州のバンドは好きなミュージシャンの曲をストレートなカバーではなく、原曲よりも魅力的にアレンジして自分のものにしてしまう傾向があるように思える。
先日、久し振りに本作を聴きなおしたのであるが、とてつもなく純粋なロックがバッチリ演奏されていてちょっと感動してしまった。「サタデーナイト」や「どうしようもない恋の唄」を聴くと、やっぱりいいな、と思ってしまう。
しかし、ちょろっと検索してみたら、かなりの高額になっていることが判明!! これじゃ若きルースターズファンもつらいだろう…。他の音源も追加して再発を希望したい。
2006年01月28日
THE SLUDGEについて その6 『幻のシングル』
ついにこのシリーズも六回目。さすがに記述ばかりで音源のリリースはまだか! と熱心なスラッヂファンから怒られてしまいそうなので、ややスローペースにしてみました。
まだまだ書くことはたくさんあるのです。
今回はスラッヂ関連の作品の中でも、最もその存在が知られていないEPを紹介したい。
これはもうスラッヂ云々ではなく、ひとつのニューウェーブとして聴いてもらいたい音源である。スガワラ氏が女の子二人を連れてきてスラッヂの「夜光少年」などを録音しているのだが、今現在にこそ聴かれるべき種類のテクノポップであると思う。
手作り感覚に溢れたジャケット、女の子の素直な歌、そして不可思議なアレンジ。
当時のシーンにおいても、これをカテゴライズするなどというのは愚かしい行為であろう。まったく何にも似ていない極私的な音楽だ。突然変異というよりは、別の現実に在り続ける感覚である。
楽曲の打ち込みのリズムは、一聴するところ、TR808あたりのキック音に聴こえなくもないが、実はドクターリズム一台で長時間を費やしてシーケンスを組んだものだという。これは昨今の何でもデジタルで簡単に編集をしているテクノ系ミュージシャンにはマネのできない偉業である。ローランドのリズムマシンを使った者なら分かると思うが、あれを別のシーケンサーに同機させるというのは相当な労力を要する。せっかく組んでも微妙にずれていたり、不可思議な効果によってスネアの音が消えてしまったりと、幾たびのハプニングに見舞われるのである。
そんな大変な作業で、大抵は出来上がってもしょぼいだけのテクノポップ止まりというのがオチなのであるが、このシングルはあのキック音のチープさが逆に良い方向へ作用していて、苦労が実っているように私には思える。
もともとの曲がカッコイイというのはあるが、アレンジにおける執念といった視点からも、私はこのシングルを評価したい。素晴らしいニューウェーヴサウンドである。
スラッヂといえばスガワラ氏の迫力のある捻れたボーカルというイメージがあるが、ここでは女の子ボーカルの起用によって完全にポップな別の曲として「夜光少年」も生まれ変わっている。スラッヂの音楽が好き、というヒトが聴いたら「?」と思うかもしれないが、私は別モノとしてこれは良質なレコードだと思う。
興味深いのは、現在音響系ヒップホップと呼ばれている音楽に質感が似ていることだ。敢えてこのようなビートを持ってくるヒップホップ系の人たちは多いし、ポップな楽曲も新しさがある。似ているヒップホップアーティストは…、アンチコン周辺のWhy?あたりだろうか。ロックのスタイルをヒップホップのビートで、なおかつポップで奇怪な装飾もつけて提供しているというのは、なかなか凄いことであると思うのだが…。
補足すると、このシングルは、当時18歳の専門学校生であった島田春美さんと14歳の女子中学生の子が歌い(スガワラさんも後ろで歌っているが)、スラッヂとは違う質感でありながら、どこかが共通したあの狂った感じを堪能できるというレコードである。プレス数は500枚ぐらいで、そのうち何枚売れたのかは不明である。
できればこれも再発したいなぁ…。とは思うのだけれど、一刻も早くスラッヂ本体の方を世に送り出したいので、ひとまずは紹介だけさせていただきました。でも、いずれはこれも正式に出したいです。
2006年01月25日
FRICTION 「ed '79 Live」
いま過去のエントリーをずっと眺めていて、FRICTIONについて書いていないことに気づいた。忘れていたのではなく、もう既に書いたつもりになっていたのが原因である。
さて、このフリクションのライヴ盤は「軋轢」発売前に録音されたもので、正式にリリースされている音源の中では一番本来のフリクションらしい音が聴ける良質なアルバムである。最近になって突如CDで発表されたわけなのだが、聴きなおしてみるとけっこう荒削りな感じで「軋轢」より全然かっこいい。
以前恒松さんに聞いた話によると、レック氏があの再発では全て指揮していたらしく、もともと音質の悪かった音源をなんとかあそこまでの状態にまでしたらしい。
まさに完璧な一枚であるが、セットでついてきたDVDの方は…、まぁ資料的には貴重なんだけど。
やはりナマで当時のフリクションを見てみたかったなぁ、というのはあるが、現在CDという記録媒体のおかげで、こうして当時の演奏を好きなときに聴けるのだから、文明の進歩には感謝したいと思う。
※以下はフリクションを未聴だという方のために書くので、既に知っている、またはもう疲れたという人は読まなくても大丈夫です。
軋轢が始まると、周囲の景色が変貌してしまう。
それまでの日常が、常識が、自分のPositionが、明らかに狂っていく。
人間の軋轢、精神の軋轢、現象の軋轢。
どんな軋轢にしろ、結末はいつもアレだ。
激しく衝突したまま、ゆっくりと落下していくイメージ。
金属的なものから、天災のような惨事までが同時多発的に侵入してくる。
パンクでもロックでも何でもよかった。方法論に縛られてしまうことは不幸だからだ。
ただ一度のミスもせずに軋轢を知ることができる者は、今後絶対に軋轢を知ることはできないだろう。
だから、誤りが正解に近づくのだ。
もう、暗い部屋で一人血を流しているだけじゃ、時代は変わらなくなってしまったのである。
2006年01月22日
THE SLUDGEについて その5 『三田寛子と骨太ロック』
三田寛子の魅力を文章で表すなどというのは無駄な努力であろう。GOROか何かに載った彼女の水着写真のインパクトたるや、人種や世代を超えた影響力をもってして現在まで息づいている。
彼女の楽曲はやはりあの初々しい歌声によって信じられないような劇的効果を発揮している。
デビュー曲「駆けてきた処女」は井上陽水という天然サイケな作曲者の手によるものであるが、実際に楽曲へ命を吹き込んでいるのは三田寛子のボーカルだ。でなければ、あの曲があそこまでの魔力を保有しえたとは考えられない。
そして、三田寛子といえばスラッヂの片岡理氏である。
片岡氏は熱心な三田寛子ファンで、あるときテレキャスターに三田寛子のステッカーを貼り付けてライヴへ登場し、他メンバーを唖然とさせたというエピソードもある。ちょうど、スラッヂが骨太ロックをコンセプトとして活動していた頃だったため、三田寛子のパブリックイメージからするとバンドにとっては異質な空気だった筈である。
その後、片岡氏は三田寛子に捧げる曲コンテストのようなイベントで見事優勝!! 「握手した手は洗わない」と断言するほどの嬉しさを見せていたという。
片岡氏のソロにおけるフリークアウトさや、スラッヂでのあの屈折しまくったテレキャスの金属的な音を知っている者ならば、このエピソードは意外に思えるかもしれない。だが、よくよく聴いてみれば、片岡氏の根底にあるものが歌謡曲と骨太ロックがぐちゃぐちゃに入り交ざった不定形な物質であることに気づかされる。
テレキャスというのは、もともと図太い音を出すギターではなく、カントリー系のミュージシャンに愛用されていたギターである。それをあれほどまでに強烈に切り込んでいくかのような音で弾いたのは私は片岡氏以外には知らない。
サウンド面で、片岡氏の使っていたエフェクターというのは、某楽器店で3000円程度で売られていたファズをスガワラ氏がプレゼントしたものをずっと使っていただけだという。それ以外にエフェクターは使用していなかったらしい。
そのエフェクトペダルは、金属製のいかにも鉄板といった感じの筐体で、中身も電池ボックスのスペースと基盤一枚といったシンプルな作りであった。そのエフェクターは繋げておくだけですでに異音を発し、踏むと爆発したようなフィードバック音が鳴り響く凄まじい一品だったという。
しかしながら、テレキャスとそのエフェクターがあったところで、そこいらのギタリストにはあの強烈な演奏はできないだろうと思う。片岡氏の演奏は『何かが狂って』いた。この世のものとも思えないような、背筋の凍る残忍さを感じることもあれば、限りなく優しい温かみを感じるときもある。まったく別の次元から発せられているようで、確実に現実を切り刻んでいるような、なんとも形容し難い性質の演奏であるが、それは片岡氏以外にはできないものなのだ。
たしかにコンセプトは骨太のロックだったかもしれない。ただ、片岡氏の演奏から窺える自由さというのは、ロックのフォーマットを突き破って無効化するほどの驚異であったことだけは確かである。
2006年01月19日
THE SLUDGEについて その4 『AFTER THE SLUDGE』
ついに片山氏ともお会いして、スラッヂファンとしては恐縮する一面、どんどん色々なエピソードを聞かせていただいて狂喜してしまいました。菅原氏と片山氏の話から得た情報をそのまま文章にしたら本が一冊できてしまいそうな濃い情報が盛りだくさんで、ここにはちょっと書けないようなこと(例えば灰野敬二が…××)もこっそり教えていただいたりして、もう何とお礼を言っていいか分からない状態です。
そんなわけでスラッヂと当時のその周辺に関しての膨大な情報を得てしまったのであるが、それを一度に書くことはもったいないと思い、まずは順を追ってセカンド・シングルの紹介をしたい。もちろん、少しづつスガワラさんや片山さんにお聞きした内容も混ぜていくので、このスラッヂについてシリーズは今後もかなりの長期に渡って書き続けていこうと思っている。
全国のスラッヂファンは今こそその思いをここでコメントしてほしい。
このセカンドでは前作よりもサウンドがソリッドさを増し、当時のスラッヂのスローガンであった『骨太ロック』によりいっそう近づいたものとなっている。
ジャケットはスガワラさんの手によるもので、前作同様素晴らしいアートワークである。ちなみに裏ジャケは片岡さんが担当。スラッヂのジャケットセンスの良さはもっと注目されるべきものだと思う。
『工事現場でまた見つかった死体』は、前回よりもフリークさが増している演奏で、歌詞も違う。歌詞が違うと言っても、スラッヂの場合は演奏する度に菅原さんの歌詞が違うものなので、どれが正しい歌詞とは誰も断言できないようになっている。菅原さんはその場で思いついたフレーズなどをバッとマイクに向けて歌うのであるが、あとで気に入った箇所はノートに書き写すなどしていたらしい。一応後に残すつもりはあった、と菅原さんは語っていた。
『窓辺のアルルカン』はスラッヂの中でもかなりノリのいい曲で、ライヴの音源でも凄まじい勢いの演奏を聴ける。けっこうこの曲をベストに挙げるファンも多かったのではないだろうか? あと、この曲に関しては「おもしろい客」のエピソードがあるのだが、それは次回にまとめて紹介したいと思う。スラッヂ周辺にはどういうわけか面白い人物や変わった人々が多く登場するのである。
『生』は美しい曲だと思う。スラッヂの演奏はギターという楽器をとにかくフリーキーに鳴らしていた。後の凡百のギターロックバンド勢には無い、ある種のオリジナルな狂気を持ってして構成されているのだから、当然の結果なのかもしれないが、実際に音を聴くと度肝を抜かれる。スラッヂとはそういうバンドなのだ。
このセカンド、世に出ているスラッヂの音源の中では最も優れた内容であると思う。聴きやすいのに物凄く深く、そして純粋にカッコイイ『ロック』であるという点で、これはスラッヂ入門には最適な一枚かもしれない。
いったい何の影響を受けたらこんな世界になるのだろうか? と思っていたら、菅原さんからたいへん興味深いことを聞いたのでその言葉で締めたいと思う。
「影響を受けたのは…、湊マサコだね。あれは凄い影響を受けた」
本当に、底知れないバンドである。
2006年01月15日
THE SLUDGEについて その3 『箱男』
スラッヂの一枚目を改めて聴いてみて思うのは、やはりその独特の世界があまりにも特異かつ洗練されたものだったということだろう。
まず、ジャケットが素晴らしい。黄色は注意を促す色であるが、ここでの効果的な使用法には恐れ入る。箱男の文字も懲りまくった書体だ。
内容は更に謎を深める。『工事現場で見つかった死体』という曲では既にタイトル通りの「工事現場で見つかった死体」以外の意味を最初からかなぐり捨てている。これをシュールレアリスムというだけで片付けてしまうのは早とちりというものであろう。ここでの『工事現場』を高次の現場として比喩してみても良いし、なぜ死体が見つからなければならなかったのか、なぜ死体がそこにあるのか? といった疑問を聴き手側で生成してみるのも面白い。スラッヂの世界には主体的な決定権が不在になっているからだ。
二曲目『夜光少年』では「硬い光の中じゃ目も見えない」という一文が現れる。光の硬度について言及するロマンティシズムの鋭さはやはり文学的な質感を感じてしまうが、それと同様に「黒い家具」や「受話器のベル」といった象徴的なモノが配置されている限り、それはやはりスラッヂの一部分なのだろう。
表題曲『箱男』は一曲目から、物語の開始の意味を持って始まっている。ここではダンボールの箱の中で生きる男が描かれているが、そこでの絶望感は無い。全てをシャットアウトしてしまうような拒絶ではなく、ある程度外部の侵食を許した上での拒絶に見えるのは、ダダイズムに内在するコミカルな一面なのかもしれない。
三曲目の異色作『恋するギャルソン』はおそらく少女の狂気をダイレクトに一人称で表現したものである。ここで少女という定型を持たない精神状態のシンボルを挿入することによって、スラッヂの物語性が大幅に狂気を帯びる。しかしながら、客観的に楽しめる類の異質さであるからこそ、ここでの物語は聴き手に突き放されないのだ。むしろ、愛着を感じるような迷路である。
駆け足で全曲紹介してしまったが、サウンド面での解説をしなかったのはやはり自分自身の手でスラッヂの世界を覗き見て欲しいからであり、文章での音楽説明ほど事実を歪めてしまうものもないと思ったからである。
それにしても、とんでもないレコードだ…。
2006年01月11日
THE SLUDGEについて その2
顔の無い人間がいたとする。その人物が泣いているのか、笑っているのか、怒っているのかは客観的には分からない仕組みだ。しかし、それが確実に「生きている」のだということだけはハッキリと分かる場合がある。
スラッヂはまさにその状態だと思う。
情報のほとんどが得られにくい状況で、音源も入手困難。たまにその名は出されるものの、伝説として、自分ではない他人の曖昧な記憶から語られる言葉から、一体何が引き出されるというのだろう。
この状態はTHE SLUDGEの音楽にとっても、それを好む者にとっても歯がゆいものだ。あんなに素晴らしいものが、それを欲する者に届かないという現状を何とかして好転させるには、スラッヂの演奏記録をまとめて世に送り出すしかない。
THE SLUDGEは死んでいない。
ここ数日の間、スラッヂの音源を聴き続けた。
「RED CROSS」には本当に感動して、久し振りにギターで弾いてみたりもした。
この音源を出さなかったら絶対に後悔する…。そんな気持ちがどんどん強まっていった。そして、スラッヂの音楽がまだしっかりと生きていることに気がついた。涙が出そうだった。
スラッヂの演奏からはサイケデリックなニオイがすることがときどきあって、それは絶対に片岡さんが発しているものだと思っていたのだが、実はそれが菅原さんのものであったというのも新しい発見であった。
特に『窓辺のアルルカン』はずっと片岡さんのギターだと思っていたものが、実は菅原さんが弾いていると聞いて驚いた。
スラッヂの独特の酩酊感は片岡さんのナチュラルに歪んだ資質と、菅原さんの持つ深い混沌とした世界がうまく解け合わさって生まれているように思える。
菅原さんが大学のとある部に入部したとき、隣の部室からまるでフリクションのようなとてつもない演奏が聞こえてきて、覗いてみたらそれが片岡さんの演奏であったというTHE SLUDGE結成以前のエピソードを聞いたとき、片岡さんのソリッドな音はフリクションにも通じるものであったことに気がついた。
そして菅原さんの悪夢のようなあの詞こそが、スラッヂにサイケな香りを与えていたのだという気がしてきたのである。
スラッジの演奏には今聴いても時代背景を一切感じさせないスタイリッシュさがある。大抵の音楽は時代の空気を余分に吸い込んでしまいがちであるのだが、スラッジに関しては周囲の空気を拒絶でもしているかのように、THE SLUDGEそのものであり続けている。
そしてそんな性質の演奏であるからこそ、もっと世に伝播させたいと思うのだ。
2006年01月09日
THE SLUDGEについて その1
THE SLUDGEは本物のロック・バンドである。
私がTHE SLUDGEに初めて触れたのは、曖昧な記憶なのだが確かライヴカセットであったように思う。ものすごい不思議な質感の楽曲と他の何にも似ていない世界観、そして圧倒的なギターの音。THE SLUDGEというバンドのイメージに私は心酔していた。
その後、シングル二枚と片岡氏のソロなどを入手し、更に深みへハマって行った。もう海外のどんなバンドよりもスラッジの音にやられた。
あるときブラッディ・バタフライのオムニバスでdip the flagがスラッジの名曲「RED CROSS」をカヴァーしていたのを聴き、THE SLUDGEのオリジナルのスタジオ録音での「RED CROSS」が聴いてみたくなった。しかし、どうやら「RED CROSS」のスタジオ録音盤というのは世に出ていないようで、いくら探してもTHE SLUDGEの演奏する「RED CROSS」は聴けないままだった。
何年も経って、スラッジのことを思い出すきっかけになったのは自分のこのブログだった。スラッジの一枚目である「箱男」と同名の小説を紹介したときに、Yさんからコメントを頂いて徐々に記憶が蘇ってきたのである。
急いで実家のレコード棚を探してみると、片岡さんのソロ作二枚がでてきた。スラッジの二枚はどこか奥の方へ入っているのか、見つけることができなかったのであるが、久し振りに聴きなおした片岡さんの楽曲にはとんでもない衝撃を受けた。
それからしばらく経って、ついに先日、ふとしたきっかけからなんと、THE SLUDGEのボーカルであるスガワラさんにお会いできた。
上野の喫茶店で、スラッジのことや当時の貴重なお話を色々と聞かせてもらえ、更にTHE SLUDGEの未発表音源、ライヴ音源などが詰まった素晴らしいCDまで頂いた。もう感無量である。
私の失礼な質問にもいろいろと答えていただき、その上未発売の音源まで聞かせてもらって、本当にスガワラさんとTHE SLUDGEの皆さんには感謝しきれない。
スガワラさんからは色々と興味深いエピソードを聞かせていただいた。
当時の片岡さんがゴム長と作業着でライヴに来たりしたこと、永寿日朗が青山に開いていた伝説的なスペース「発狂の夜」のライヴの様子、ヤマジさんとTHE SLUDGEのメンバーが一緒にスタジオへ入ったら、ヤマジさんがスラッジの楽曲をすべて完璧に弾いたこと、スガワラさんが片岡さんと初めて出会ったときのことなど、とてもここには書ききれないほどたくさんのエピソードを語ってもらえた。
本当はインタヴュー形式で掲載しようかと思ったのだけれど、それはまたの機会にきっちりとまとめたいのでひとまずはこういった形で書いておきたい。
昨日は家で一人、スガワラさんから頂いたCD-Rを聴き続けた。特に、大好きだった「RED CROSS」は何度も聴いた。未発売のスタジオ録音、そしてライヴ音源。どちらもこのまま埋もれてしまうのはもったいない魅力に満ち溢れているし、THE SLUDGEという素晴らしいバンドがあったことをもっと知ってもらいたいと思った。
そして実は、THE SLUDGEの音源をまとめて再発しようという話が持ち上がっている。
これは絶対に再発されるべきであるし、ネット上でTHE SLUDGEを検索してもまったくヒットしない現状を考えたら早急に対処すべきだと思う。THE SLUDGEの演奏が忘れられてしまっては文化的に重大な喪失であるからだ。
だから、私もTHE SLUDGEの再発に携わることに決めた。
いろいろと権利関係の問題もあると思うので、さすがに私が勝手にプレスしたりすることはできないが、THE SLUDGEのメンバー、関係者の方々と話し合って何とか今年中には店頭に並ぶように進めたいと思う。できる限りのことはしていきたい。
ここまで入れ込んだバンドはTHE SLUDGEが初めてであるし、それほどにまでRED CROSSでの片岡さんが弾くテレキャスの音が強烈であったのである。
どういう形で関っていくかは未定だが、私は何らかの形でTHE SLUDGEには恩返しがしたいのだ。
タイトルに「その1」とあるように、THE SLUDGEに関してはこれからも何回かに分けてじっくりと紹介していきたいと思うし、いずれは皆さんへ素晴らしい音源そのものを届けたいと思う。
最後に、忙しい中わざわざ私のような一ファンのために時間を割いてくれたスガワラさんと、THE SLUDGEのメンバー皆さんに感謝します。本当にありがとうございました。
今後ともTHE SLUDGE再発に向けてよろしくお願いします!
2006年01月05日
VID-SEX
2005年12月03日
村八分 「ライブ」
ロックンロールは悪魔の音楽だった。ストーンズにしろブラック・サバスにしろ、彼らが黒魔術的な方法の一つとしてロックを選択した若者たちであったことは旧知の事柄である。
海外のサタニズムのニオイがするロック・カルチャーは、ミック・ジャガーがケネス・アンガーの映画にあのようにして関ったことからも推測できるように、ドラッグ漬けの悪魔崇拝から成り立っているものである。それは土着的な習慣や信仰へのカウンターとして機能していたものであるため、日本での効果は現地のそれと比べるとイマイチな感じがしないでもなかった。
では、日本にそのような悪魔の音楽をやるバンドがいなかったのか? と問うならば、いたのである。しかもとんでもないバケモノバンドとして今も伝説化されて語り継がれているバンドだ。
そのバンドこそがこの村八分である。
チャー坊の歌詞は日本特有のカウンターであり、サタニズムに代わる武器として吐き出された。ドラッグの影響丸出しのメンバー写真、冨士夫のとにかくかっこいいギターフレーズ、インパクトのありすぎるステージ、そしてその強烈なバンド名などで、あまり表にだされることはなかったバンドであるが、影響力は凄まじいものであった。
いままでは主にこの二枚組みライブだけが入手しやすい音源であったわけだが、先日ついにボックスセットが発売され(しかもDVD付き!)、封印が解かれたこの村八分。日本で最も凶悪で危険なロックをやっていた彼らの演奏を改めて聴いてみると、やはり魔術的な印象はあるものの、その日本でしか成し得なかったであろうサタニズムに代替する迫力がしっかりと息づいており、本物のロックの恐ろしさを思い知った。
それにしても、チャー坊と冨士夫のルックスは本当に恐い。学生時代、街でこんなのに絡まれたら嫌だなぁ、というどうでもいいことをよく考えた。本物の不良の持つ迫力が、村八分の存在に更に拍車をかけていたことは事実であろう。
これから村八分を聴いてみよう、という方にはぜひあのボックスをオススメしたい。内容がいいボックスセットなんて滅多にないが、アレは買って損はないと思う。未発表音源やDVDだけでなく、この『ライブ』もリマスタリングされて完全復刻で入っている。
「本物のロック」という言葉を幻想で片付ける前に、この演奏だけは聴いてもらいたい。
間違いなく、これはロックである。
2005年12月02日
山口冨士夫 『PRIVATE CASSETTE』
ついに村八分のボックスが発売され、その充実した内容に感動したわけなんですが、よく考えたら山口冨士夫のソロに関しては書いていなかったので改めてここで紹介。
まずはプライベートカセット。これがおそらく冨士夫音源の中で最も素晴らしく、サイケデリックな質感も伴った異色ともいえる一枚だと思う。再発されて本当によかった。
特にラストの『STONE』はラリーズを経由した冨士夫が独自のサイケデリックを打ち出した決定的な一曲であると思うし、他の弾き語りもすべて純粋な歪み方をしている。
村八分でのストーンズ風の楽曲が好きという人にも、ここにある純粋なロックを聴いてもらいたい。ジャケットもクスリの香りがぷんぷんする風景であるが、ここにある音との相性は最高だ。日本のロックを代表する一枚として、村八分以外の冨士夫作品を一枚選べと言われたら私は絶対にこれを挙げる。
二曲目の『Just Friend of Mind』の「サングラスかけたまま泣いてた」とか、聴いてるこっちが泣きそうになるフレーズも最高にクール。『捨てきれっこないさ』とか、本当にしみじみとするいい歌が詰まっている。
2005年10月03日
Franz Ferdinand
ついに買ったこのセカンド!! 素晴らしいです。
一枚目も良かったのですが、この二作目は段違いの傑作で、もはや彼らは職人の域に達しています。
リズムがものすごくしっかりしているので、ノレる曲調だし、歌詞もいいです。
とんでもない人達がでてきたものですね。グラスゴーというのはすごい土地です。
80年代のポップスやニューウェーブを通過したTレックスといった感じでしょうか? なかなか一言じゃ表現できないニューサウンドです。
ひょっとしたら個人的に今年のベストになるかもしれません。クオリティ高過ぎ。もう何も言えません。とにかく素晴らしい新譜です。と、何か薄っぺらな感想で申し訳ありません…。あまりにも良いのでなかなか上手く書けないんです。とにかく名作!!
2005年07月26日
Neil Young 「Greatest Hits」
Like A Hurricaneを、へろへろなバージョンでカバーしたら、ようやくこの人のナチュラルな幻覚風景が見えてきた。ニール・ヤングはドラッグだ。それはとても深く覚醒するためのスタッフである。
アルバム「ハーヴェスト」や「アフター~」もいいが、最近作での洗練されたロックもいい。すべてがニール・ヤングという規律の中で不気味に配置されているが、このベスト盤ではそれが無くなるのではないか? と往年のファンたちに危惧されたものの、出来上がってみれば素晴らしい選曲で、やっぱりニール・ヤングはいつの時代も変わってなどいないのである。
選曲がいいというより、曲ひとつひとつが輝いている。そのためどれをどう並べても、ニールヤングという宇宙が完成する仕組みになっているのだろう。
2005年06月22日
THE POLICE
どさくさに紛れてこのような王道の名盤を紹介してみるのもたまにはいいでしょう。
ポリスはよく聴くとヘンなんです。
この盤に収録されているデビュー曲『ロクサーヌ』も、繰り返し聴くとかなり奇妙。
中学のときテレビの音を消して、ポリスを一日中流すのが日課だった。
勉強もできない、友達が多いわけでもない、更にまったくモテないという当時の空気を、スティングの線の細いボーカルとアンディ・サマーズのテレキャスターは、恥ずかしいぐらいくっきりと映し出す。
だから、しばらくポリスは聴いていない。
たまに町でポリスの曲を耳にすると、中学の頃の行き詰った虚無感を思い出し、吐き気がするほどロマンチックになる。
2005年06月15日
SYZE 「UPPER NIGHT」
伊藤耕と川田良の最強ロックコンビが組んだこのSYZE。「T.V.EASY」や「無力のかけら」など、SEX時代の名曲もアレンジ違いでここに再録。そんな最高のレコードなのに、知名度はいまひとつ。変形10インチ(くらいかな)という大きさのせいなのか、それともみんなフールズやSEXだけで満足しているのかは不明であるが、あの二人のファンであるなら絶対に聴く価値のある一枚。
本物のロックを演奏できる数少ないミュージシャンが伊藤耕と川田良であり、その二人の音源なのだからハズレなわけがない。そんな気持ちでこの盤に接すれば、絶対に後悔はしない筈であるし、根気よく中古盤屋の棚を漁る行為も報われるだろう。
ガチガチのロックンロールが好きだという人には、ぜひこのレコードを聴いてほしい。勢いのある音圧がロックとは何なのか? という初歩的な疑問を払拭してくれるであろうから。
2005年05月05日
喝!タルイバンド
僕は朝っぱらから会社で何をやっているのだろう?
こんな古いレコードのジャケットスキャンして、しかも休日だというのに。
ダンスそうじき♪ などと鼻歌を歌ったところで未来は絶望だ。
でなければ某ゲイ雑誌用の原稿をこんな朝っぱらから書くようなマネは常人にゃあ無理だべ。
まぁ、締め切り忘れた僕が悪いのですが…。
まさか連休中に締め切りなんて、不意打ちもいいところですね。
さて、この喝!タルイバンド、いまだに活動しているというのだから恐れ入る。
僕も少しは彼らを見習い、物事を継続したり、最後までやり抜くような、
そんな立派な姿勢を保てるようになりたいものである。
2005年05月02日
Badfinger 「ノー・ダイス」
悪い指。パワー・ポップっていうのはこれが元祖なわけですが、ビートルズの弟分というだけで片付けられているのが現状。
彼らの中ではこのアルバムが一番完成度高く、特に5、6曲目の流れは完璧にポップ。いろんな人がカバーして有名なわりに、原曲を知っているという人は稀。
なぜここまで評価が低いのかといえば、それは値段が高すぎるから。
アップルレコードは中古でも2000円以上するので、この人たちも高いまま。最近出た紙ジャケの国内盤も2800円ぐらいする。
もっと手軽な価格にすれば、彼らの評価も変わると思うのだが、東芝EMIは今後も価格を下げることはしないんでしょうね。可哀想なバンドです。
2005年04月12日
ザ・バッヂ 「タッチ」
あきれた顔の少年少女の横っ面を、
思いっきり張り倒す。
教育であり、権力を誇示する意味もある。
だから、あいつらはガムをくちゃくちゃ噛み続ける若者が嫌いなのだ。朝から晩まで道徳の基準を探し、工場の床に転がる無数のネジを拾い集めることしかできない。何せ汗と油にまみれての結果が微々たる給料なのだから、彼が失望に満ちた瞳になるのは当然の成行きなのかもしれなかった。
髭剃り跡を左手でこすりながら、何種類かの死を分別する。
彼の一日は、ちっとも美しくない。
歌謡曲だなんだと言われても、これは間違いなく日本最強のパワー・ポップバンドである。甘酸っぱい青春の一枚。CD化して未発表音源なんかも発売されたけど、あのころ聞いたザ・バッヂの曲は、やっぱり特別だったのかもしれない。
2005年03月16日
ティアドロップス
2005年03月01日
ザ・フゥー 「リーガル・マター」
2005年01月24日
午前四時 「LIVE BOOTLEG」
午前四時に街をうろついているアブナイひとたちを見ると、ついつい怖くなって電柱の陰に身を隠してしまいますね。そして、そこからじっくりと観察。深夜の人達は何でも溶かしてしまう液体を口内から発射したりして、大変迷惑だったりします。で、それを防ぐために必要なのがこのレコードです。
やたらと金属質なギターにロックなボーカル。一時は灰野敬二がいたらしいけど、その時代の音源は残ってないっぽいです。持ってる人はブートで流せ! と言いたいところですが、このバンド好きな人って何人ぐらいいるんでしょうね。僕はもちろん真剣に好きですけど、もう解散してるわけだし、あんまり過去にすがり付いてばかりいるというのも大人げないね。反省しました。
Jeff Beck 「truth」
最近妙に忙しい。別に多忙なサラリーマンのように朝からダッシュですし詰めの電車へ突っ込んでいくような苦労は無いのだが、やることが多いというのは良いことなのか悪いことなのか。
そんな疑問にぶち当たったらこれ。基本的にジェフ・ベックはそんなに好きじゃないし、インテリぶった態度がムカつきもする。ただ、この一枚は色んな意味で考えさせてくれる一枚だ。だからジェフ・ベックは嫌いだけどこのアルバムは評価したい。
ロッドスチュワートのヴォーカルが派手すぎたりしたときに、ギターの音を壊さないような絶妙のタイミングで構成された楽曲は、ギターバンドにとっては模範的すぎる。ここまでタイトにまとめられると、逆に奇怪な感じがしてならない。で、珍しくわりとハードなこともやってるんで、後のジェフベックが嫌いな人でも結構楽しめると思います。
2005年01月21日
ザ・ジャム イン・ザ・シティ
ポール・ウェラーはジャムよりスタカンの方が…。そんなことを言うオシャレなやつには、これを爆音で聴くことをオススメする。決してスタイル・カウンシルとは同じ音楽ではない。スタカンのオシャレな感覚とは別のスタイリッシュさがこの盤の魅力だ。
いきなり飛び出すポール・ウェラーのVOXアンプ直結ギターに後頭部を強打されたような衝撃を受け、立て続けに飛び出してくるモッズサウンドにはもうため息しか出ない。
この渋すぎる直球ロックンロールは、当時の博多ロックシーンで大流行。ロッカーズもルースターズもみんな聴いてたモッズの聖典みたいな一枚だが、個人的にはやっぱりスタカンの方がいいので、もうこのアルバムを聴くこともないかもしれない。でも、たまにはロックンロール! ということで最高です。
2005年01月15日
CCR 「GREEN RIVER」
クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイバル最高! こんなレコード他に無いですね。
泥臭さがある一定の基準からはみ出してしまうと極めて化学的な物質に変化するという一例。サイケと言われればそうだけど、ロック中のロック。
それにしてもここまで霊的にロックなアルバムは他にジミヘンの「エレクトリックレディランド」くらいしかないだろう。稀に見る奇異な精神世界である。
後期のアルバムも捨てがたいし、「マルディグラ」の奇怪な音も好きだが、やはりCCRと言ったら初期の三枚。特にこれは短くて聴きやすいのに、聴いた後のどんよりした曇り空のような感覚が体験できる不思議なレコードだ。
ただの「アメリカのロック」から、そろそろCCRを解放してあげたいものである。彼らの音楽は他のどんなものよりも純粋に曇っていた。
グリーン・デイ 「ワーニング」
最初に「ドゥーキー」とか聴いて「だっせぇ」と思った。それでしばらくはグリーンデイなんて聴いて無かったんだけど、このアルバムが出たとき「マイノリティ」がラジオで流れてて、それなりに良かったため、このアルバムを聴いた。
かつてのメロコアスタイルではなく、ポップなロック。しかもかなり真剣、というところに魅力がある。はっきり言って「ドゥーキー」みたいな何も考えてないような馬鹿丸出しサウンドを持続していたら、彼らはただの一発屋以外の何でもなかっただろう。しかし本作を聴いて、グリーンデイがマトモにロックしている姿を見せつけられたら、もう否定できない。僕にとってはどうでもいいバンドだったけど、このアルバムからの彼らはストレートにカッコよく、かなり見直した。誤解を恐れずに言えば名盤である。
剥き出しの青春、やりたいことが一つしかない喜びといったものに接すると、何とも言えない悲しい気持ちになる。本作は僕にとって「泣けるアルバム」なのかもしれない。他人の前向きな姿勢を見ると、深く落ち込むという人にこそ聴いてほしい一枚である。
2005年01月13日
ガスタンク 「ジェロニモ」
インディアンはウソつかない。つまり虚実を許さないのである。それは正義とは少し違い、ただの変人の暴君扱いされても仕方が無い。だからこそこのシングルの凄味は増してくるのである。
歌詞がヤケクソでカッコよく(サソリ砂漠サボテン頭聳え立つぜモヒカン!)、特に「たたかえーじぇろにもっもっもぉぉぉ」のところが好き。他の曲がメタルっぽいガスタンクであるが、このシングルではもはやへヴィなヤケクソロック以外の何でもなくなっている。これ一枚あったらもうガスタンクは大丈夫。燃えます。
ちなみにB面もふっきれたようなポップパンクで「?」な感じです。
2005年01月10日
カーズ
2005年01月06日
サムライ 「セレクト」
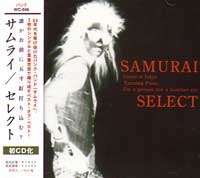
明けましておめでとうこざいます。去年は何一ついいことが無かったので、今年こそは幸せになりたいものですね。
さて、結局正月はだらだら腐った生活を送ってしまい、主にこれ聴いてました。サムライのベスト的内容。と、ただそれだけで何やらただ事じゃないのは分かりますね。何せあのサムライです。僕は昔リューシンのサックスをライブで聴いて相当にビビッたのですが、本盤はまだ彼がベース・ボーカルのパンクをやってたころのサムライというバンドのほぼ全曲集なのです。
久々に聴いてあまりに剥き出しなロックンロールに赤面しつつも、やっぱりこういう真剣な音楽っていいなぁ、などとごろごろ寝転がりながら新年を迎えることができ、再発してくれたいぬん堂さんには一応感謝したいところです。
2004年12月24日
コクシネル

ピナコテカから出た三角変形ジャケの有名なレコード。で、最近CDで再発されたんだけど、コクシネルってやっぱすごいなぁ、と感動。前衛でもポップでもなく、静かに風景を形作っていく音楽である。
懐かしい景色や、御伽噺のような世界観をぎこちない演奏で構築していくコクシネルの演奏形態は特異であり、いつの時代でも有効なクスリである。
だから、この盤に今から触れても決して遅くないし、聴いて何の感想も持たないというのも有りだと思う。演奏がヘタクソだとか、音質が悪いと言われても、このレコードは個人的に大好きだ。だから、次のボーイズツリーの方も、少し整った音になってしまっていたが、かなり聴き込んだ。
こういう「うた」が素直に響くレコードの良さに世間の注目が集まり始めてから、それに答えるように様々な名盤が再発されたり新譜で出たりといった現象が起きて、こういった音源さえも簡単に聴けるようになった。喜ばしい限りである。