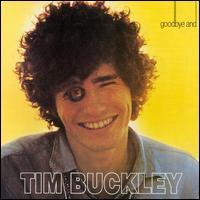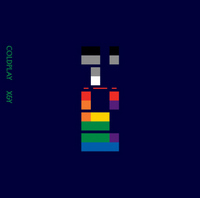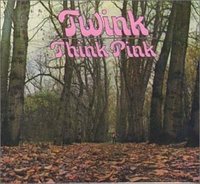凝解、その後 書き手・森本
世の中の右と左そしてうしろ 暗がりで笑う人をみたときや 銀行のATMで現金を取り忘れたときに なんとなく読むブログ
« 2006年02月 | メイン | 2006年04月 »
2006年03月のアーカイブ
2006年03月29日
Controlled Bleeding
後にいろんなことをやって、ことごとく中途半端な仕上がりになっていた彼らの初期作品。ここではかなりの暴力的なハーシュノイズになっている。
でも、この路線で突き進むよりはヘンなエレボデやデスメタみたいなことをやっている彼らの方が好感が持てるし、姿勢としておもしろいと思う。
純粋にノイズが好きな人にとってはこれが一番なのかもしれないけれど、CBの魅力は他の情けない部分にこそあると思うので、あまりみの盤をもてはやすことはここではしないでおく。
まずはCBの音に触れてみて、それを受け入れるか拒絶するかを聴き手が選ぶことが重要だと思うので、未体験ならば一度触れてみてください。
2006年03月23日
Jackson Browne
初期ジャクソン・ブラウンの良さは歌詞にあるとよく言われているが、本当は三作目までのあの霊的なアコースティック・サウンドがそれを引き立てていたことはあまり語られないでいる。
一枚目ではもっともストレートな形でジャクソン・ブラウンという男の世界が表現されているが、あの質感の完璧さや、生活感の溢れる空気を社会的なステージを意識させる歌詞を前にすると、思わずため息が漏れる。
やはり彼の世界は地に足の着いた理想を引き寄せるような、広く一般的すぎる努力の過程をドラマティックに構成しているようにも思える。
ここで薄汚い政治性を持ち出さなかったのは、やはり彼が詩人であり、フィクションの中での作業を望んでいたからだと思うし、あの不思議な土の匂いが混ざったサウンドを耳にすると、その心地よい世界にしばらく滞在したくなる欲求にも駆られる。
後の彼はバンドサウンドを強化してしまい、初期の頃にあったような美しい風景は描かなくなってしまった。それはLate For The Skyで涙した我々にとっては大きな喪失である。
久し振りに彼の一枚目を聴きなおすと、忘れていた風景がふいに思い起こされたりして、なんだか切なくなる。
2006年03月22日
大江慎也 「THE GREATEST MUSIC」
メンバーは大江、花田、井上、池畑の4人、まさに初期ルースターズの復活盤とも言える究極の一枚である。
ここまで完全な、理想的ともいえる復活を遂げるとは、UNの時点ではまったく思いもしなかった。
楽曲は参加メンバーから分かるように、ルースターズ初期の「あの」感じである。懐かしくもあるが、極めて現代的とも言えるこのアルバムは、あまりにも素直であるが故にその素直さの絶対性を定義づけてしまっている。
というわけで、ルースターズを知らない者にとってはここにある素直さ、ストレートさが異様なものとして映る可能性も否定できない。なるべくなら、大江慎也という人物の過去の音源や経歴を踏まえてから本作を聴いたほうが、妙な誤解は抱かなくて済むと思う。
まずはPVでの動き回る大江を見てもらえれば、このアルバムへの気合いがいかなるものかがよく理解できると思う。
本物のロックンロールが、また楽しめるのである。
2006年03月21日
SIMON & GARFUNKEL
霊的なもの。
彼らの歌を呪詛であるという人間がいないのは、彼らの歌が疑問ではなく解答であるからだ。
はじめから解答しか出されていないものに対して、誰も疑問を抱く者はいない。
そして、絶えず変化していく周囲があるからこそ、サイモンとガーファンクルは「呪術的ではないありふれたもの」として存在しているのである。もし仮に彼らの歌が変化し続けているとするなら、それ以外の存在に彼らが含有されることは無かったであろう。
いろいろな意味で、現実を見つめさせられる一枚であるが、人によっては「すこぶるありふれたもの」として聴かれてしまうのであろう。それがアーティストとしての死に繋がらないのは、ポピュラリティーという威力の絶大さを物語っているようにも見える。
2006年03月20日
Tim Buckley
ティム・バックリィの悲痛な感覚はまだここでは表立ってはいない。
彼がただのシンガーソングライターの一人として語られないのは、その世界の深さが底なしに広がっているからであり、サイケデリックが局所的に訪れていた季節ではなかったことを思い知らされる。
ファンタジックな広がりではなく、わりと人間的な臭みを含んでいる部分も良心的と言えるかもしれない。ティム・バックリィのサウンドや詩は確かな手ごたえのようなものを聴き手に与える。
ジャケからカントリー風の演奏をイメージするかもしれないが、ここにあるのは紛れも無いアシッド漬けの心象風景である。
聴くにはそれなりの覚悟が必要だが、深いダメージを受けるような歌ではないのがせめてもの救いであろう。
歴史的傑作。
2006年03月18日
片岡理 「寒いおでんは背中から。」CD盤
捻れたような日常内の白昼夢をイメージしがちであるが、このCD盤でのアプローチはアナログの時よりも真摯で美しい狂気に彩られている。片岡氏の中に息を潜めて存在していた現実離れした現実が、よりキレイな形で表出している。
ラストの「埒開かずの海」での混沌は特に深い。中途半端な飾り物の狂気が多い中で、こうした純度の高い本物の狂気を目の当たりにすると、思わず駆け出したくなるような恐怖におそわれる。
日本の音楽史を見渡しても、ここまで異質な感覚を保有したものは他に無い。
もちろん、ジャンルや時代性で語られるべき性質のものではないし、何かと比較できるものでもない。これはあまりにもストレートに歪曲しているからだ。
狂気的なものと毅然とした態度で向き合うというのはかなり辛いことであるが、具体的なものを普遍化しようとするような昨今の歌謡曲の悪辣さに比べたら、ここにある狂気は何事にもたじろがない強い意志に基づいて構築されているために偉大であると感じられる。
このCDを聴くと、思考することの無力さを徹底的に突きつけられたような気がする。考えを放棄させるのではなく、考えること自体を封じ込められてしまう。
このCDはジャケットも素晴らしいし、内容もアナログ盤とは違う録音なので、片岡氏の狂気に惚れ込んでしまった者ならば一度は聴いておきたいものだ。入手は困難であると思うが、再発希望の声があれば何とかして出してみたいものである。
ここにあるスラッヂのあのギター音とはまた違った狂い方の楽曲が、片岡氏の本質部分を覗き見ることができるものなのかどうかは不明であるが…。
一言でいうなら、恐ろしいまでの傑作である。
2006年03月16日
COLDPLAY 「X&Y」
静寂の中で蠢くメロディは、はっとするぐらい美しい瞬間がある。
コールドプレイのこのアルバムは、異常なまでの緊張感と神経すべてが麻痺するような美しさに満ちている。さすがに冬場は体温を奪われそうでそんなに聴かなかったのだが、気候が春めいてきたので久し振りにプレイヤーにセットしてみた。
「Speed Of Sound」の繊細さと沈み込むような感覚は異様である。ここまでのものはそうそう出てくる音ではないし、コールドプレイが頭一つ抜けたセンスを持っていることはこの楽曲を聴いたことのあるものならば理解できると思う。
ただ、明らかに癒しの音楽ではないので、病床に伏しているときなんかは聴かない方がいい。取り殺される危険性もまた魅力だと言えるのかもしれないが…。
2006年03月15日
Belle and Sebastian 「The Life Pursuit」
2000年以降の音楽に極端に弱い私も、たまには新譜を購入するわけです。
で、久し振りに買ったのがこのベルセバ。今年で10周年とのことで、ただならぬ気合いを感じてついつい購入してしまいました。
中の音はもうグラスゴー特有のネオアコ・ギターポップですね。先日ユージニアスを紹介しましたが、グラスゴーというのは本当に独特のバンドが多い地域です。
ひたすらポップにまとめられたベルセバの新作ですが、肩の力を抜いてわりとリラックスして作られているような感触がすでに大物の貫禄を感じさせます。
輸入盤にはボーナスでDVDもついているそうですが、私は間違えて国内盤を購入してしまったが故に映像は拝めませんでした…。
今日はベルセバの内容があまりに誠実な感じがしたので、レビューもマジメに書きます。
斬新なアイディアも今回は盛り込まれているのですが、それを意識させないストレートなポップ・ミュージックとしての良さが素晴らしく、彼らのアルバムの中でもかなりの傑作なのではないかと思います。
全曲しっかりしたポップミュージックなので、なるべくならアルバム一枚通しで聴いてほしい作品です。グラスゴーのシーンは今後も注目していきたいと思います。
2006年03月14日
EUGENIUS 「Oomalama」
2006年03月13日
TWINK 「THINK PINK」
よく言われる「名盤」といった感じの華やかさよりも、しっかりとした表現の力強さを感じる良作だと思う。ピンクスもいいが、たまにはこっちも聴くとバランスがとれ、思わぬ袋小路へ迷い込むというような失敗は免れられるだろう。
こういった有名なレコードは、まずジャケットのイメージが広く伝播し、次に中の音を聴いてショックを受けた者たちが、まるで神秘体験でも語るかのように口伝していくものである。
キツネでも憑いたかのような目つきで、熱っぽくこういった音楽を語ろうとも、本質的な部分でそれが相手に伝わることは少ない。だから、こういったものを紹介したいのならば、まずはその音を実際に体験してもらう必要がある。
だが、大抵の音楽ファンはそこまでして他人のオススメするレコードを聴こうとはしない。なぜなら、説明の最中に彼らは「この音楽については認識できない」と判断してしまうからであり、無意識のうちに拒絶してしまっているからだ。つまり、理解の及ばぬ不可解なものに貴重な人生を消費したくない、と数学的に計算してしまうからなのである。
ここで重要なのは、音楽の情報を得たとき、または得るときは、なるべく余計な雑念を打ち消しておくべきだということだ。邪念が入ってしまうと、根拠の無い未聴作品への否定が始まり、結局死ぬまでその音楽を聴かずに過ごすことになってしまう。それではあまりにももったいない。
トゥインクのような音楽は、決して万人が称賛するようなものではないが、それでも、まったく聴きもしないで軽蔑しているようなら、一度購入してじっくり聴いてみることを勧めたい。きっとあたらしい風景のうちの一つにはひっかかるだろうから…。
2006年03月09日
JELLY BELLY
かつて一世を風靡したギャルバン、伝説の一枚。
なんだかんだいって結構好きでした。
誰にも言わずにこっそり聴いてました。
そんな甘酸っぱい思い出のEP。もう10年近く経つのか…。
内容は90年代の女の子バンドを象徴するものですね。あの頃のギャルバンの魅力が全部詰まってる。ボーカルスタイルも演奏のポップさも、いまだにフォロワーを生み続けているぐらいの影響力で、ジェリベリを知らないという人も多いものの、知っている人は熱狂的に支持しているというバンドであった。
メンバーは解散後もそれぞれ活動を続けているが、やっぱりこのバンドが一番甘酸っぱくて好きだ。
90年代のあの気の抜けたような雰囲気の中、一瞬で駆け抜けたこの演奏は、ポップでありつつも、何かしらの強い信念は貫徹していたように思える。
毎度のことながら、このEPも現在は入手困難なので、デモ音源やコンピの音源も入れてCD化を希望したい。
たまにはこういうのもいいですね。
2006年03月08日
The Moody Blues 「Every Good Boy Deserves Favour」
ムーディーブルースの最高傑作とされている本作だが、改めて聴くとその異様な雰囲気にびっくりする。一体何が彼らをここまでにさせたかは不明だが、私もなぜか買った記憶は無いのにアナログとCDを一枚づつ持っている。
わりと重い音楽だが、壮大なストーリーを描こうとして拡大ではなく逸脱に向かってしまったのがよくわかる仕組みになっており、当時のプログレブームに一石を投じるどころか全身で身投げしてしまっているような捨て鉢さも感じる意欲作である。
メンバーの気合いだけは尋常ではないので、作り手の強い意志や創作への熱い思いに触れたいときはこのアルバムを聴くといいかもしれない。
2006年03月07日
CACTUS
カクタスの一枚目はとんでもない。
もう針を落として数秒後には爆音でふっ飛ばされそうになる。
この一曲目ほど強烈なハードロックも無いだろう。とにかく気合いのこもった本物の「ハードロック」演奏が炸裂しているすごい曲である。
ただ、一曲目のインパクトが強烈過ぎるがゆえに、後半の楽曲は霞んでしまっているような気がしてならない(客観的すぎる意見で申し訳在りません)。
この一曲目の尋常じゃない勢いを未体験ならば是非一聴することをオススメしたい。いままで持っていたハードロックの認識が大きく覆されることは確実である。
カーマイン・アピスの暴れまくるようなドラミングは何にしても必聴。
2006年03月06日
Animal Collective
2006年03月04日
アケボノイズ
不気味な、不可解なもののイメージを、決してコミカルにすることなく「違和感を違和感として」楽しませることの出来るイメージとして生成していたのがこのバンドである。
なんとも不思議としかいいようのない、不気味でポップなニューウェイヴサウンド。まさに隠れた名盤の名に相応しい出来である。
最初からコンセプトを背負って出てきたバンドよりも、こういう他者から見て理解の及ばぬようなオリジナリティを持っているバンドの方が印象的だ。アヴァンギャルドとポップを繋いでいるものがここにあるような得体のしれない存在なのだということを、音楽好きは見過ごしがちである。
「かごめ」という日本の土着的な言葉の発音が結果的にここにある世界の入り口としては分かりやすいヒントとなって転がっているが、そのカギを拾ってしまうと、もう後戻りは出来なくなっているというのも素敵な要素の一つである。
2006年03月03日
人間クラブ
南浩二のロックスターぶりには誰もかなわない。後に大江によってあそこまで完成されたバンドになったルースターズであるが、この人間クラブの時点では南のアクの強さが前面に出ており、当時の北九州にこんなバンドがあった、という事実以上のインパクトをこの残された音源から感じ取れる。
南のヴォーカルスタイルはサンハウスの菊にそっくりであるが、やはりロックンロールしているという点では誰も否定できるものではない。
楽曲は村八分などのパクリっぽいものであるが、これは大江が村八分ファンであったからであり、盗作なんかではなく愛のこもったオマージュといった感じだ。サンハウスの「レモンティー」もそうだが、九州のバンドは好きなミュージシャンの曲をストレートなカバーではなく、原曲よりも魅力的にアレンジして自分のものにしてしまう傾向があるように思える。
先日、久し振りに本作を聴きなおしたのであるが、とてつもなく純粋なロックがバッチリ演奏されていてちょっと感動してしまった。「サタデーナイト」や「どうしようもない恋の唄」を聴くと、やっぱりいいな、と思ってしまう。
しかし、ちょろっと検索してみたら、かなりの高額になっていることが判明!! これじゃ若きルースターズファンもつらいだろう…。他の音源も追加して再発を希望したい。
2006年03月02日
HALF YEARS
大好きな加害妄想レコード。ジャケはソフトな感じだが、中身はハードなジギャク節。藤井氏のセンスはいつも最高だ。
愚鈍やバスタードに比べると、活動期間の短さもあってかあまり語られないバンドだが、このEPの気合いは物凄い。というより加害妄想はいいレーベルだったと実感できます。
愚鈍のカセット「腐臭」のピアノの音とノイズまみれのハードコアを聴いて以来、ずっと愚鈍周辺は何か特別な感触があったのであるが、やはりその斬新な空気を作り出していたのは藤井氏であったと思う。ここでのプレイはそこまで極端なものではないが、初期愚鈍で聴けるものと共通の凄みは持ち合わせていると思う。天才藤井氏が残したジャパニーズ・ハードコアの佳作である。
2006年03月01日
あざらし
日本特有のデカダンス(任侠、寺山、ザ・スターリン)などの世界を極端に凝縮して、パンクサウンドで拡大してみせたのがあざらしである。
ここ最近のバンドの中ではその潔い姿勢が目だち、かなり気に入っている。
ボーカルのメグ子嬢はJ.A.シーザーやナゴム関連などもバッチリ聴き込んでいるそうで、今後の活躍が楽しみな逸材だ。
初期の頃はスターリンのカバーをやったりして直球のハードパンクだったのだが、最近リリースされたカセットに収められた『夜の底』なんかを聴くとその幅の広さとテクニックの向上に驚かざるをえない。ついにあざらしもここまできたか~、などと嬉しくなってしまう。
活動を再開したので、そろそろフルアルバムも出して欲しいのだが、メグ子嬢もライヴなどで忙しいらしいので、レコーディングはじっくり腰をすえて頑張ってもらいたいものである。